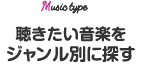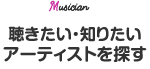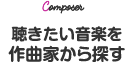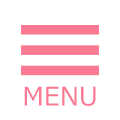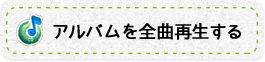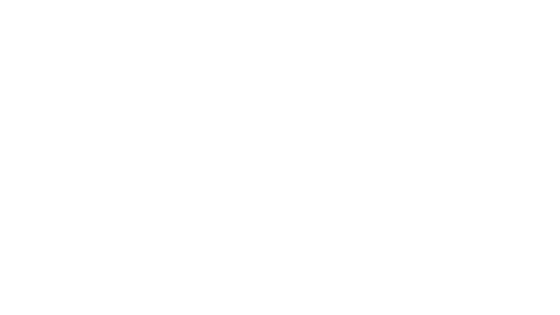![]()
ブラームス ピアノ三重奏曲1番3楽章 動画集
ブラームス ピアノ三重奏曲 第1番 第3楽章の動画集です。

ブラームス ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 作品8
第3楽章 アダージョ
BRAHMS Piano Trio No.1 in B major Op.8
3rd mov. Adagio
ブラームスのピアノ三重奏曲第1番 第3楽章です。
ヴァイオリン、チェロ、ピアノのための三重奏曲です。
本作品には2つの稿が現存しています。
1. ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 第3楽章 / ブラームス,ヨハネス / 磯野 順子
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 第3楽章
本作品には2つの稿が現存する。第1稿は1853-54年に作曲、ジムロック社から出版された。そして1889年に作品の出版権がブライトコプフ・ウント・ヘルテル社に移った際、ブラームスは主題の差替え等、大幅な改訂を施し、今日一般に演奏される稿を完成させた。
第3楽章 Adagio H-dur 4/4拍子。ABA’の3部形式。A部の主題はピアノと弦パートの応答。B部は快活な主題、付点リズムの動機による応答、主題変奏から成る。主題のリズムと跳躍音形はA部の主題後楽節を思わせる。A’部ではピアノが後楽節を装飾し、切れ目なく続くピアノの音色と声部進行がA'部全体の統一感を高めている。
作曲家解説 - ブラームス,ヨハネス
ドイツの作曲家。19世紀ドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者。ドイツ音楽における「三大B」とも称される。ドイツロマン派の代表的な作曲家といえる。
ハンブルクに生まれ、ウィーンに没した。音楽家である父から最初の手ほどきを受けたあと、地元ハンブルクの教師からピアノや作曲を学んだ。1853年、生涯の友人となるヴァイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒムと知り合ったほか、ワイマールにリストを訪ね、9月にはかねてより理想的な音楽家と考えていたロベルト・シューマンとデュッセルドルフで会見し、激賞を受けた。翌年、自殺未遂を図ったシューマンの一家を援助するべくデュッセルドルフを再訪。シューマン夫人のクララとは当初恋愛感情で、後に深い友情をもって終生交流が続いた。
1862年、拠点をハンブルクからウィーンへ移した。ウィーンではすぐに芸術界に受け入れられ、次第に活躍の場を広げた。1868年には同地に定住を決意。この時期、指揮者としての演奏活動も行っていたが、1875年にはこの分野から撤退。より作曲に注力するようになった。この頃には国際的な名声を確実なものとし、存命中に数々の栄誉に浴した。
ブラームスのピアノ作品は創作活動期間の初期と末期に集中して作られている。彼の音楽性の変遷を観察する上では極めて重要な作品群である。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
演奏家解説 - 磯野 順子
日本のヴァイオリニスト。
2. ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 第3楽章 / ブラームス,ヨハネス / 田中 浩子
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 第3楽章
本作品には2つの稿が現存する。第1稿は1853-54年に作曲、ジムロック社から出版された。そして1889年に作品の出版権がブライトコプフ・ウント・ヘルテル社に移った際、ブラームスは主題の差替え等、大幅な改訂を施し、今日一般に演奏される稿を完成させた。
第3楽章 Adagio H-dur 4/4拍子。ABA’の3部形式。A部の主題はピアノと弦パートの応答。B部は快活な主題、付点リズムの動機による応答、主題変奏から成る。主題のリズムと跳躍音形はA部の主題後楽節を思わせる。A’部ではピアノが後楽節を装飾し、切れ目なく続くピアノの音色と声部進行がA'部全体の統一感を高めている。
作曲家解説 - ブラームス,ヨハネス
ドイツの作曲家。19世紀ドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者。ドイツ音楽における「三大B」とも称される。ドイツロマン派の代表的な作曲家といえる。
ハンブルクに生まれ、ウィーンに没した。音楽家である父から最初の手ほどきを受けたあと、地元ハンブルクの教師からピアノや作曲を学んだ。1853年、生涯の友人となるヴァイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒムと知り合ったほか、ワイマールにリストを訪ね、9月にはかねてより理想的な音楽家と考えていたロベルト・シューマンとデュッセルドルフで会見し、激賞を受けた。翌年、自殺未遂を図ったシューマンの一家を援助するべくデュッセルドルフを再訪。シューマン夫人のクララとは当初恋愛感情で、後に深い友情をもって終生交流が続いた。
1862年、拠点をハンブルクからウィーンへ移した。ウィーンではすぐに芸術界に受け入れられ、次第に活躍の場を広げた。1868年には同地に定住を決意。この時期、指揮者としての演奏活動も行っていたが、1875年にはこの分野から撤退。より作曲に注力するようになった。この頃には国際的な名声を確実なものとし、存命中に数々の栄誉に浴した。
ブラームスのピアノ作品は創作活動期間の初期と末期に集中して作られている。彼の音楽性の変遷を観察する上では極めて重要な作品群である。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
演奏家解説 - 田中 浩子
日本のピアニスト。学習院大学在学中より演奏活動を始める。学習院大学卒業と同時に武蔵野音楽大学に入学。3人の男児の母である立場から、子供のための音楽会を多数企画、演奏し、地域の音楽教育の一端を担う。自身の活動が各種音楽関係、教育関係の雑誌に掲載される。また、音楽と英語のキャリアを活かし、今までに外国人に4年間延べ100人以上英語でピアノを教える。また、起業家としては、2003年よりヒロミュージックスクールを主宰し、生徒の指導の傍ら、数々の優秀な講師陣の育成、音楽教室経営事業のコンサルタントとして活躍する。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
3. ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 第3楽章 / ブラームス,ヨハネス / 金田 真理子
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 第3楽章
本作品には2つの稿が現存する。第1稿は1853-54年に作曲、ジムロック社から出版された。そして1889年に作品の出版権がブライトコプフ・ウント・ヘルテル社に移った際、ブラームスは主題の差替え等、大幅な改訂を施し、今日一般に演奏される稿を完成させた。
第3楽章 Adagio H-dur 4/4拍子。ABA’の3部形式。A部の主題はピアノと弦パートの応答。B部は快活な主題、付点リズムの動機による応答、主題変奏から成る。主題のリズムと跳躍音形はA部の主題後楽節を思わせる。A’部ではピアノが後楽節を装飾し、切れ目なく続くピアノの音色と声部進行がA'部全体の統一感を高めている。
作曲家解説 - ブラームス,ヨハネス
ドイツの作曲家。19世紀ドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者。ドイツ音楽における「三大B」とも称される。ドイツロマン派の代表的な作曲家といえる。
ハンブルクに生まれ、ウィーンに没した。音楽家である父から最初の手ほどきを受けたあと、地元ハンブルクの教師からピアノや作曲を学んだ。1853年、生涯の友人となるヴァイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒムと知り合ったほか、ワイマールにリストを訪ね、9月にはかねてより理想的な音楽家と考えていたロベルト・シューマンとデュッセルドルフで会見し、激賞を受けた。翌年、自殺未遂を図ったシューマンの一家を援助するべくデュッセルドルフを再訪。シューマン夫人のクララとは当初恋愛感情で、後に深い友情をもって終生交流が続いた。
1862年、拠点をハンブルクからウィーンへ移した。ウィーンではすぐに芸術界に受け入れられ、次第に活躍の場を広げた。1868年には同地に定住を決意。この時期、指揮者としての演奏活動も行っていたが、1875年にはこの分野から撤退。より作曲に注力するようになった。この頃には国際的な名声を確実なものとし、存命中に数々の栄誉に浴した。
ブラームスのピアノ作品は創作活動期間の初期と末期に集中して作られている。彼の音楽性の変遷を観察する上では極めて重要な作品群である。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
演奏家解説 - 金田 真理子
日本のピアニスト。パリ国立高等音楽院をプルミエプリを取って卒業。マネス音楽院で修士号を、博士号をニューヨーク市立大学大学院で取得。
モントリオール国際ピアノコンクール、マリア・カナルス国際ピアノコンクールに入賞。国内外で交響楽団戸の共演、リサイタルを行う。また、室内楽奏者としても活発に活動。
2004年オハイオ・ウェズレヤン大学准教授に就任。ピティナ正会員。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
4. ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 第3楽章 / ブラームス,ヨハネス / テツラフ,クリスチャン
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 第3楽章
本作品には2つの稿が現存する。第1稿は1853-54年に作曲、ジムロック社から出版された。そして1889年に作品の出版権がブライトコプフ・ウント・ヘルテル社に移った際、ブラームスは主題の差替え等、大幅な改訂を施し、今日一般に演奏される稿を完成させた。
第3楽章 Adagio H-dur 4/4拍子。ABA’の3部形式。A部の主題はピアノと弦パートの応答。B部は快活な主題、付点リズムの動機による応答、主題変奏から成る。主題のリズムと跳躍音形はA部の主題後楽節を思わせる。A’部ではピアノが後楽節を装飾し、切れ目なく続くピアノの音色と声部進行がA'部全体の統一感を高めている。
作曲家解説 - ブラームス,ヨハネス
ドイツの作曲家。19世紀ドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者。ドイツ音楽における「三大B」とも称される。ドイツロマン派の代表的な作曲家といえる。
ハンブルクに生まれ、ウィーンに没した。音楽家である父から最初の手ほどきを受けたあと、地元ハンブルクの教師からピアノや作曲を学んだ。1853年、生涯の友人となるヴァイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒムと知り合ったほか、ワイマールにリストを訪ね、9月にはかねてより理想的な音楽家と考えていたロベルト・シューマンとデュッセルドルフで会見し、激賞を受けた。翌年、自殺未遂を図ったシューマンの一家を援助するべくデュッセルドルフを再訪。シューマン夫人のクララとは当初恋愛感情で、後に深い友情をもって終生交流が続いた。
1862年、拠点をハンブルクからウィーンへ移した。ウィーンではすぐに芸術界に受け入れられ、次第に活躍の場を広げた。1868年には同地に定住を決意。この時期、指揮者としての演奏活動も行っていたが、1875年にはこの分野から撤退。より作曲に注力するようになった。この頃には国際的な名声を確実なものとし、存命中に数々の栄誉に浴した。
ブラームスのピアノ作品は創作活動期間の初期と末期に集中して作られている。彼の音楽性の変遷を観察する上では極めて重要な作品群である。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
演奏家解説 - テツラフ,クリスチャン
ドイツ出身のヴァイオリニスト。
5. ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 第3楽章 / ブラームス,ヨハネス / スターン,アイザック
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 第3楽章
本作品には2つの稿が現存する。第1稿は1853-54年に作曲、ジムロック社から出版された。そして1889年に作品の出版権がブライトコプフ・ウント・ヘルテル社に移った際、ブラームスは主題の差替え等、大幅な改訂を施し、今日一般に演奏される稿を完成させた。
第3楽章 Adagio H-dur 4/4拍子。ABA’の3部形式。A部の主題はピアノと弦パートの応答。B部は快活な主題、付点リズムの動機による応答、主題変奏から成る。主題のリズムと跳躍音形はA部の主題後楽節を思わせる。A’部ではピアノが後楽節を装飾し、切れ目なく続くピアノの音色と声部進行がA'部全体の統一感を高めている。
作曲家解説 - ブラームス,ヨハネス
ドイツの作曲家。19世紀ドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者。ドイツ音楽における「三大B」とも称される。ドイツロマン派の代表的な作曲家といえる。
ハンブルクに生まれ、ウィーンに没した。音楽家である父から最初の手ほどきを受けたあと、地元ハンブルクの教師からピアノや作曲を学んだ。1853年、生涯の友人となるヴァイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒムと知り合ったほか、ワイマールにリストを訪ね、9月にはかねてより理想的な音楽家と考えていたロベルト・シューマンとデュッセルドルフで会見し、激賞を受けた。翌年、自殺未遂を図ったシューマンの一家を援助するべくデュッセルドルフを再訪。シューマン夫人のクララとは当初恋愛感情で、後に深い友情をもって終生交流が続いた。
1862年、拠点をハンブルクからウィーンへ移した。ウィーンではすぐに芸術界に受け入れられ、次第に活躍の場を広げた。1868年には同地に定住を決意。この時期、指揮者としての演奏活動も行っていたが、1875年にはこの分野から撤退。より作曲に注力するようになった。この頃には国際的な名声を確実なものとし、存命中に数々の栄誉に浴した。
ブラームスのピアノ作品は創作活動期間の初期と末期に集中して作られている。彼の音楽性の変遷を観察する上では極めて重要な作品群である。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
演奏家解説 - スターン,アイザック
ユダヤ系のヴァイオリニスト。