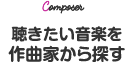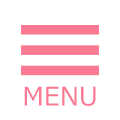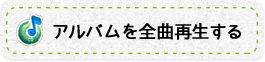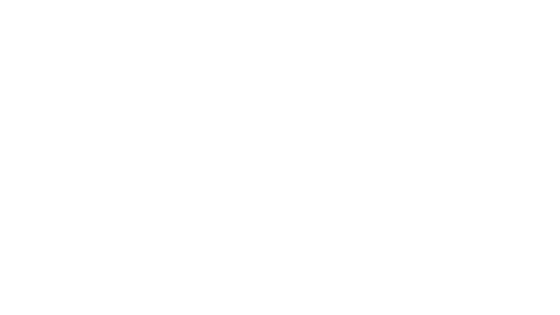![]()
ドビュッシー 版画全曲 動画集
ドビュッシー 版画全曲の動画集です。

ドビュッシー 版画 L100
DEBUSSY Estampes L100
ドビュッシー 版画の全3曲です。
全3曲からなるピアノ作品です。
印象主義的なピアノ技法を確立した作品といわれています。
ドビュッシー 版画動画集一覧はこちら
1. 版画 全曲 / ドビュッシー,クロード / 金子 一朗
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 版画 全曲
この作品はしばしばドビュッシーが印象主義的なピアノ技法を確立した作品として評される。作曲が完成した直後に書いた手紙の中で、「曲名がとても気に入っている」と書いている。また、全体は三曲から構成されており、各曲それぞれ、オリエント、スペイン、フランスから題材をとっているが、実際にドビュッシーは東洋にもスペインにも行ったことがないため、「想像でうめあわせをするしかありません」と同手紙に書かれている。
1890年代半ばごろから作曲に着手し、1903年に完成、翌年初演された。しばらくぶりの本格的なピアノ作品となる。《版画》はジャック・エミール・ブランシュに献呈されている(ただし、第二曲の〈グラナダの夕〉は、それよりはやくピエール・ルイスに献呈されている)。古典的な和声概論にとらわれないその音づかいに、当時の理論教師たちは目をむいたようだ。
〔第一曲〕塔。ドビュッシーは1889年にパリで開催された万国博覧会において、バリ島民の演奏するガムラン音楽をきき、深く興味をもった。この曲はその影響を反映したといわれている。五音音階を用いた東洋風の主題が、変化し、繰り返され、独特の雰囲気をつくりあげている。
〔第二曲〕グラナダの夕べ。ハバネラのリズム、ムーア人の歌調、ギターの響き、スペイン・アンダルシーアの古都グラナダを彷彿とさせる音楽となっている。スペインの作曲家ファリャも、この作品をきいて、ドビュッシーの天性の想像力と才能を賞賛した。三段譜が登場する。
〔第三曲〕雨の庭。繊細なアルペジオによって庭の木立にふりかかる雨が描かれる。「ねんねよ、坊や Dodo l’engant do」と、「もう森にはゆかないよ Nous n’irons plus au bois」という二つのフランス童謡からあおいだ主題を、曲中にたくみに引用してかかれている。日本的なしっとりした雨のイメージと比べると、かなりカラっとした印象がある。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
作曲家解説 - ドビュッシー,クロード
フランスの作曲家。
クロード・アシル・ドビュッシーは1862年8月22日、父マニュエルと母ヴィクトリーヌの長男として、パリ西郊約20キロの町サン=ジェルマン=アン=レに生まれた。
ドビュッシーは、ワーグナーを乗り越えるためにフランス固有の美を武器とし、大胆な語法によって20世紀音楽への扉をあけた作曲家である。長調・短調の明確な対比を嫌った彼は、教会旋法、東洋風の5音音階、全音音階などを駆使し、印象派の画家たちが遠近法を回避するために画面を分割したように、平面的、スタティックな美を生み出した。
ドビュッシーのピアニズムには、大きくわけて次の3つの源流がある。モーテ夫人を通じて伝えられたショパンの技法(ビロードのようなタッチと美しい響き、軽やかなリズムなど)、やはりモーテ夫人に目を開かれたバッハの書法(対位法的、優雅なアラベスクなど)、18世紀クラヴサン音楽の技法(多彩な装飾音、「バトリ」など)。
ドビュッシー独自の語法としては、ペダルで白鍵と黒鍵の響きを混ぜたり、重音や和音塊を平行移動させたり、いくつもの層を積み重ねて、独特の「音響宇宙」を生み出したこと、ポリリズムやルバートを多用して自在な律動を作り出したことなどがあげられる。
1907年にドビュッシーは、「私はますます音楽というのは色彩と律動づけられた時間でできていると確信するようになった」と書いているが、調性からもリズムからも自由になりながら有機性を失わなかったドビュッシーの在り方を象徴するような言葉である。
『前奏曲集第1巻』が『管弦楽のための映像』の「イベリア」と同時進行していたように、ドビュッシーのピアノ曲はオーケストラ曲やオペラ、声楽曲と密接なかかわりももつものが多い。従って、単にピアノ曲としての解釈にとどまるのではなく、背景となっているテキストや管弦楽の色彩感をとりいれなければ、片手落ちになるだろう。
ドビュッシーの「音響宇宙」にはペダルの使用が不可欠だが、彼の発想はしばしば管弦楽的で、幾重もの音響レベルを明確に弾きわけるタッチとペダリングが求められる。
東洋美術に深い関心をもち、また作品にもとりいれたドビュッシーは、作曲にあたってのモットーを「ものごとの半分まで言って想像力に接ぎ木させる」と表現している。すべてをさらけ出さず、深く静かに潜行させるその姿勢は、東洋人、とりわけ日本人の美意識にもっとも近い作曲家ということができよう。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
フランス近代の印象派を代表する作曲家。長音階・短音階以外の旋法と、機能和声にとらわれない自由な和声法などとを用いて独自の作曲を実行した。ドビュッシーの音楽は、その特徴的な和音構成などで、音の印象を表現するという独特の表現スタイルを確立し、「印象主義音楽(印象派)」と称されている。
演奏家解説 - 金子 一朗
日本のピアニスト。早稲田大学理工学部数学科卒。本職は中・高等学校の数学科教諭。ピティナピアノコンペティション ソロ部門特級は2003~4年ともに入選、コンチェルト部門上級で2004年に奨励賞、グランミューズ部門A1カテゴリーで2004年に第1位受賞、2005年ソロ部門特級でグランプリ(金賞)および聴衆賞、ミキモト賞、王子賞、日フィル賞、文部科学大臣賞、読売新聞社賞、審査員基金海外派遣費用補助を受賞。2007年3月、『ピティナ40周年記念 ピアノコンチェルトの夕べ』にて渡邊一正指揮・NHK交響楽団と共演。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
2. 版画 全曲 / ドビュッシー,クロード / 金田 真理子
音源:CD[ピアノリサイタル]より 2001年1月14日 王子ホール
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 版画 全曲
この作品はしばしばドビュッシーが印象主義的なピアノ技法を確立した作品として評される。作曲が完成した直後に書いた手紙の中で、「曲名がとても気に入っている」と書いている。また、全体は三曲から構成されており、各曲それぞれ、オリエント、スペイン、フランスから題材をとっているが、実際にドビュッシーは東洋にもスペインにも行ったことがないため、「想像でうめあわせをするしかありません」と同手紙に書かれている。
1890年代半ばごろから作曲に着手し、1903年に完成、翌年初演された。しばらくぶりの本格的なピアノ作品となる。《版画》はジャック・エミール・ブランシュに献呈されている(ただし、第二曲の〈グラナダの夕〉は、それよりはやくピエール・ルイスに献呈されている)。古典的な和声概論にとらわれないその音づかいに、当時の理論教師たちは目をむいたようだ。
〔第一曲〕塔。ドビュッシーは1889年にパリで開催された万国博覧会において、バリ島民の演奏するガムラン音楽をきき、深く興味をもった。この曲はその影響を反映したといわれている。五音音階を用いた東洋風の主題が、変化し、繰り返され、独特の雰囲気をつくりあげている。
〔第二曲〕グラナダの夕べ。ハバネラのリズム、ムーア人の歌調、ギターの響き、スペイン・アンダルシーアの古都グラナダを彷彿とさせる音楽となっている。スペインの作曲家ファリャも、この作品をきいて、ドビュッシーの天性の想像力と才能を賞賛した。三段譜が登場する。
〔第三曲〕雨の庭。繊細なアルペジオによって庭の木立にふりかかる雨が描かれる。「ねんねよ、坊や Dodo l’engant do」と、「もう森にはゆかないよ Nous n’irons plus au bois」という二つのフランス童謡からあおいだ主題を、曲中にたくみに引用してかかれている。日本的なしっとりした雨のイメージと比べると、かなりカラっとした印象がある。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
作曲家解説 - ドビュッシー,クロード
フランスの作曲家。
クロード・アシル・ドビュッシーは1862年8月22日、父マニュエルと母ヴィクトリーヌの長男として、パリ西郊約20キロの町サン=ジェルマン=アン=レに生まれた。
ドビュッシーは、ワーグナーを乗り越えるためにフランス固有の美を武器とし、大胆な語法によって20世紀音楽への扉をあけた作曲家である。長調・短調の明確な対比を嫌った彼は、教会旋法、東洋風の5音音階、全音音階などを駆使し、印象派の画家たちが遠近法を回避するために画面を分割したように、平面的、スタティックな美を生み出した。
ドビュッシーのピアニズムには、大きくわけて次の3つの源流がある。モーテ夫人を通じて伝えられたショパンの技法(ビロードのようなタッチと美しい響き、軽やかなリズムなど)、やはりモーテ夫人に目を開かれたバッハの書法(対位法的、優雅なアラベスクなど)、18世紀クラヴサン音楽の技法(多彩な装飾音、「バトリ」など)。
ドビュッシー独自の語法としては、ペダルで白鍵と黒鍵の響きを混ぜたり、重音や和音塊を平行移動させたり、いくつもの層を積み重ねて、独特の「音響宇宙」を生み出したこと、ポリリズムやルバートを多用して自在な律動を作り出したことなどがあげられる。
1907年にドビュッシーは、「私はますます音楽というのは色彩と律動づけられた時間でできていると確信するようになった」と書いているが、調性からもリズムからも自由になりながら有機性を失わなかったドビュッシーの在り方を象徴するような言葉である。
『前奏曲集第1巻』が『管弦楽のための映像』の「イベリア」と同時進行していたように、ドビュッシーのピアノ曲はオーケストラ曲やオペラ、声楽曲と密接なかかわりももつものが多い。従って、単にピアノ曲としての解釈にとどまるのではなく、背景となっているテキストや管弦楽の色彩感をとりいれなければ、片手落ちになるだろう。
ドビュッシーの「音響宇宙」にはペダルの使用が不可欠だが、彼の発想はしばしば管弦楽的で、幾重もの音響レベルを明確に弾きわけるタッチとペダリングが求められる。
東洋美術に深い関心をもち、また作品にもとりいれたドビュッシーは、作曲にあたってのモットーを「ものごとの半分まで言って想像力に接ぎ木させる」と表現している。すべてをさらけ出さず、深く静かに潜行させるその姿勢は、東洋人、とりわけ日本人の美意識にもっとも近い作曲家ということができよう。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
フランス近代の印象派を代表する作曲家。長音階・短音階以外の旋法と、機能和声にとらわれない自由な和声法などとを用いて独自の作曲を実行した。ドビュッシーの音楽は、その特徴的な和音構成などで、音の印象を表現するという独特の表現スタイルを確立し、「印象主義音楽(印象派)」と称されている。
演奏家解説 - 金田 真理子
日本のピアニスト。パリ国立高等音楽院をプルミエプリを取って卒業。マネス音楽院で修士号を、博士号をニューヨーク市立大学大学院で取得。
モントリオール国際ピアノコンクール、マリア・カナルス国際ピアノコンクールに入賞。国内外で交響楽団戸の共演、リサイタルを行う。また、室内楽奏者としても活発に活動。
2004年オハイオ・ウェズレヤン大学准教授に就任。ピティナ正会員。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
3. 版画 全曲 / ドビュッシー,クロード / 石井 晶子
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 版画 全曲
この作品はしばしばドビュッシーが印象主義的なピアノ技法を確立した作品として評される。作曲が完成した直後に書いた手紙の中で、「曲名がとても気に入っている」と書いている。また、全体は三曲から構成されており、各曲それぞれ、オリエント、スペイン、フランスから題材をとっているが、実際にドビュッシーは東洋にもスペインにも行ったことがないため、「想像でうめあわせをするしかありません」と同手紙に書かれている。
1890年代半ばごろから作曲に着手し、1903年に完成、翌年初演された。しばらくぶりの本格的なピアノ作品となる。《版画》はジャック・エミール・ブランシュに献呈されている(ただし、第二曲の〈グラナダの夕〉は、それよりはやくピエール・ルイスに献呈されている)。古典的な和声概論にとらわれないその音づかいに、当時の理論教師たちは目をむいたようだ。
〔第一曲〕塔。ドビュッシーは1889年にパリで開催された万国博覧会において、バリ島民の演奏するガムラン音楽をきき、深く興味をもった。この曲はその影響を反映したといわれている。五音音階を用いた東洋風の主題が、変化し、繰り返され、独特の雰囲気をつくりあげている。
〔第二曲〕グラナダの夕べ。ハバネラのリズム、ムーア人の歌調、ギターの響き、スペイン・アンダルシーアの古都グラナダを彷彿とさせる音楽となっている。スペインの作曲家ファリャも、この作品をきいて、ドビュッシーの天性の想像力と才能を賞賛した。三段譜が登場する。
〔第三曲〕雨の庭。繊細なアルペジオによって庭の木立にふりかかる雨が描かれる。「ねんねよ、坊や Dodo l’engant do」と、「もう森にはゆかないよ Nous n’irons plus au bois」という二つのフランス童謡からあおいだ主題を、曲中にたくみに引用してかかれている。日本的なしっとりした雨のイメージと比べると、かなりカラっとした印象がある。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
作曲家解説 - ドビュッシー,クロード
フランスの作曲家。
クロード・アシル・ドビュッシーは1862年8月22日、父マニュエルと母ヴィクトリーヌの長男として、パリ西郊約20キロの町サン=ジェルマン=アン=レに生まれた。
ドビュッシーは、ワーグナーを乗り越えるためにフランス固有の美を武器とし、大胆な語法によって20世紀音楽への扉をあけた作曲家である。長調・短調の明確な対比を嫌った彼は、教会旋法、東洋風の5音音階、全音音階などを駆使し、印象派の画家たちが遠近法を回避するために画面を分割したように、平面的、スタティックな美を生み出した。
ドビュッシーのピアニズムには、大きくわけて次の3つの源流がある。モーテ夫人を通じて伝えられたショパンの技法(ビロードのようなタッチと美しい響き、軽やかなリズムなど)、やはりモーテ夫人に目を開かれたバッハの書法(対位法的、優雅なアラベスクなど)、18世紀クラヴサン音楽の技法(多彩な装飾音、「バトリ」など)。
ドビュッシー独自の語法としては、ペダルで白鍵と黒鍵の響きを混ぜたり、重音や和音塊を平行移動させたり、いくつもの層を積み重ねて、独特の「音響宇宙」を生み出したこと、ポリリズムやルバートを多用して自在な律動を作り出したことなどがあげられる。
1907年にドビュッシーは、「私はますます音楽というのは色彩と律動づけられた時間でできていると確信するようになった」と書いているが、調性からもリズムからも自由になりながら有機性を失わなかったドビュッシーの在り方を象徴するような言葉である。
『前奏曲集第1巻』が『管弦楽のための映像』の「イベリア」と同時進行していたように、ドビュッシーのピアノ曲はオーケストラ曲やオペラ、声楽曲と密接なかかわりももつものが多い。従って、単にピアノ曲としての解釈にとどまるのではなく、背景となっているテキストや管弦楽の色彩感をとりいれなければ、片手落ちになるだろう。
ドビュッシーの「音響宇宙」にはペダルの使用が不可欠だが、彼の発想はしばしば管弦楽的で、幾重もの音響レベルを明確に弾きわけるタッチとペダリングが求められる。
東洋美術に深い関心をもち、また作品にもとりいれたドビュッシーは、作曲にあたってのモットーを「ものごとの半分まで言って想像力に接ぎ木させる」と表現している。すべてをさらけ出さず、深く静かに潜行させるその姿勢は、東洋人、とりわけ日本人の美意識にもっとも近い作曲家ということができよう。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
フランス近代の印象派を代表する作曲家。長音階・短音階以外の旋法と、機能和声にとらわれない自由な和声法などとを用いて独自の作曲を実行した。ドビュッシーの音楽は、その特徴的な和音構成などで、音の印象を表現するという独特の表現スタイルを確立し、「印象主義音楽(印象派)」と称されている。
演奏家解説 - 石井 晶子
日本のピアニスト。武蔵野音楽大学音楽学部ピアノ専攻卒業。2002年第3回フランス音楽コンクール(全日本演奏家協会主催)、2005年第3回全日本ピアノデュオコンクール(同協会)にてそれぞれ入賞。ソロ、ピアノデュオ活動だけでなく、伴奏・室内楽も活発に行っている。演奏活動の他、勉強会・講習会・コンサートプロデューサーとしても活動し、いくつものプロデュースを成功させている。(社)全日本ピアノ指導者協会正会員。全日本演奏家協会正会員。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
4. 版画 全曲 / ドビュッシー,クロード / 大竹 道哉
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 版画 全曲
この作品はしばしばドビュッシーが印象主義的なピアノ技法を確立した作品として評される。作曲が完成した直後に書いた手紙の中で、「曲名がとても気に入っている」と書いている。また、全体は三曲から構成されており、各曲それぞれ、オリエント、スペイン、フランスから題材をとっているが、実際にドビュッシーは東洋にもスペインにも行ったことがないため、「想像でうめあわせをするしかありません」と同手紙に書かれている。
1890年代半ばごろから作曲に着手し、1903年に完成、翌年初演された。しばらくぶりの本格的なピアノ作品となる。《版画》はジャック・エミール・ブランシュに献呈されている(ただし、第二曲の〈グラナダの夕〉は、それよりはやくピエール・ルイスに献呈されている)。古典的な和声概論にとらわれないその音づかいに、当時の理論教師たちは目をむいたようだ。
〔第一曲〕塔。ドビュッシーは1889年にパリで開催された万国博覧会において、バリ島民の演奏するガムラン音楽をきき、深く興味をもった。この曲はその影響を反映したといわれている。五音音階を用いた東洋風の主題が、変化し、繰り返され、独特の雰囲気をつくりあげている。
〔第二曲〕グラナダの夕べ。ハバネラのリズム、ムーア人の歌調、ギターの響き、スペイン・アンダルシーアの古都グラナダを彷彿とさせる音楽となっている。スペインの作曲家ファリャも、この作品をきいて、ドビュッシーの天性の想像力と才能を賞賛した。三段譜が登場する。
〔第三曲〕雨の庭。繊細なアルペジオによって庭の木立にふりかかる雨が描かれる。「ねんねよ、坊や Dodo l’engant do」と、「もう森にはゆかないよ Nous n’irons plus au bois」という二つのフランス童謡からあおいだ主題を、曲中にたくみに引用してかかれている。日本的なしっとりした雨のイメージと比べると、かなりカラっとした印象がある。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
作曲家解説 - ドビュッシー,クロード
フランスの作曲家。
クロード・アシル・ドビュッシーは1862年8月22日、父マニュエルと母ヴィクトリーヌの長男として、パリ西郊約20キロの町サン=ジェルマン=アン=レに生まれた。
ドビュッシーは、ワーグナーを乗り越えるためにフランス固有の美を武器とし、大胆な語法によって20世紀音楽への扉をあけた作曲家である。長調・短調の明確な対比を嫌った彼は、教会旋法、東洋風の5音音階、全音音階などを駆使し、印象派の画家たちが遠近法を回避するために画面を分割したように、平面的、スタティックな美を生み出した。
ドビュッシーのピアニズムには、大きくわけて次の3つの源流がある。モーテ夫人を通じて伝えられたショパンの技法(ビロードのようなタッチと美しい響き、軽やかなリズムなど)、やはりモーテ夫人に目を開かれたバッハの書法(対位法的、優雅なアラベスクなど)、18世紀クラヴサン音楽の技法(多彩な装飾音、「バトリ」など)。
ドビュッシー独自の語法としては、ペダルで白鍵と黒鍵の響きを混ぜたり、重音や和音塊を平行移動させたり、いくつもの層を積み重ねて、独特の「音響宇宙」を生み出したこと、ポリリズムやルバートを多用して自在な律動を作り出したことなどがあげられる。
1907年にドビュッシーは、「私はますます音楽というのは色彩と律動づけられた時間でできていると確信するようになった」と書いているが、調性からもリズムからも自由になりながら有機性を失わなかったドビュッシーの在り方を象徴するような言葉である。
『前奏曲集第1巻』が『管弦楽のための映像』の「イベリア」と同時進行していたように、ドビュッシーのピアノ曲はオーケストラ曲やオペラ、声楽曲と密接なかかわりももつものが多い。従って、単にピアノ曲としての解釈にとどまるのではなく、背景となっているテキストや管弦楽の色彩感をとりいれなければ、片手落ちになるだろう。
ドビュッシーの「音響宇宙」にはペダルの使用が不可欠だが、彼の発想はしばしば管弦楽的で、幾重もの音響レベルを明確に弾きわけるタッチとペダリングが求められる。
東洋美術に深い関心をもち、また作品にもとりいれたドビュッシーは、作曲にあたってのモットーを「ものごとの半分まで言って想像力に接ぎ木させる」と表現している。すべてをさらけ出さず、深く静かに潜行させるその姿勢は、東洋人、とりわけ日本人の美意識にもっとも近い作曲家ということができよう。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
フランス近代の印象派を代表する作曲家。長音階・短音階以外の旋法と、機能和声にとらわれない自由な和声法などとを用いて独自の作曲を実行した。ドビュッシーの音楽は、その特徴的な和音構成などで、音の印象を表現するという独特の表現スタイルを確立し、「印象主義音楽(印象派)」と称されている。
演奏家解説 - 大竹 道哉
日本のピアニスト。東京音楽大学、研究科を首席で卒業。読売新人演奏会出演。第53回日本音楽コンクール入選。 87~90年ベルリン芸大留学。優等を得て卒業。
07年にはじめてのCD、「バッハ・ピアノリサイタル」(ライブ録音)を発売、「レコード芸術」で高い評価を得る。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
5. 版画 全曲 / ドビュッシー,クロード / 金田 真理子
音源:CD[ピアノリサイタル]より 2001年1月14日 王子ホール(東京)にて 「ピティナ・ピアノ曲事典」より
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 版画 全曲
この作品はしばしばドビュッシーが印象主義的なピアノ技法を確立した作品として評される。作曲が完成した直後に書いた手紙の中で、「曲名がとても気に入っている」と書いている。また、全体は三曲から構成されており、各曲それぞれ、オリエント、スペイン、フランスから題材をとっているが、実際にドビュッシーは東洋にもスペインにも行ったことがないため、「想像でうめあわせをするしかありません」と同手紙に書かれている。
1890年代半ばごろから作曲に着手し、1903年に完成、翌年初演された。しばらくぶりの本格的なピアノ作品となる。《版画》はジャック・エミール・ブランシュに献呈されている(ただし、第二曲の〈グラナダの夕〉は、それよりはやくピエール・ルイスに献呈されている)。古典的な和声概論にとらわれないその音づかいに、当時の理論教師たちは目をむいたようだ。
〔第一曲〕塔。ドビュッシーは1889年にパリで開催された万国博覧会において、バリ島民の演奏するガムラン音楽をきき、深く興味をもった。この曲はその影響を反映したといわれている。五音音階を用いた東洋風の主題が、変化し、繰り返され、独特の雰囲気をつくりあげている。
〔第二曲〕グラナダの夕べ。ハバネラのリズム、ムーア人の歌調、ギターの響き、スペイン・アンダルシーアの古都グラナダを彷彿とさせる音楽となっている。スペインの作曲家ファリャも、この作品をきいて、ドビュッシーの天性の想像力と才能を賞賛した。三段譜が登場する。
〔第三曲〕雨の庭。繊細なアルペジオによって庭の木立にふりかかる雨が描かれる。「ねんねよ、坊や Dodo l’engant do」と、「もう森にはゆかないよ Nous n’irons plus au bois」という二つのフランス童謡からあおいだ主題を、曲中にたくみに引用してかかれている。日本的なしっとりした雨のイメージと比べると、かなりカラっとした印象がある。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
作曲家解説 - ドビュッシー,クロード
フランスの作曲家。
クロード・アシル・ドビュッシーは1862年8月22日、父マニュエルと母ヴィクトリーヌの長男として、パリ西郊約20キロの町サン=ジェルマン=アン=レに生まれた。
ドビュッシーは、ワーグナーを乗り越えるためにフランス固有の美を武器とし、大胆な語法によって20世紀音楽への扉をあけた作曲家である。長調・短調の明確な対比を嫌った彼は、教会旋法、東洋風の5音音階、全音音階などを駆使し、印象派の画家たちが遠近法を回避するために画面を分割したように、平面的、スタティックな美を生み出した。
ドビュッシーのピアニズムには、大きくわけて次の3つの源流がある。モーテ夫人を通じて伝えられたショパンの技法(ビロードのようなタッチと美しい響き、軽やかなリズムなど)、やはりモーテ夫人に目を開かれたバッハの書法(対位法的、優雅なアラベスクなど)、18世紀クラヴサン音楽の技法(多彩な装飾音、「バトリ」など)。
ドビュッシー独自の語法としては、ペダルで白鍵と黒鍵の響きを混ぜたり、重音や和音塊を平行移動させたり、いくつもの層を積み重ねて、独特の「音響宇宙」を生み出したこと、ポリリズムやルバートを多用して自在な律動を作り出したことなどがあげられる。
1907年にドビュッシーは、「私はますます音楽というのは色彩と律動づけられた時間でできていると確信するようになった」と書いているが、調性からもリズムからも自由になりながら有機性を失わなかったドビュッシーの在り方を象徴するような言葉である。
『前奏曲集第1巻』が『管弦楽のための映像』の「イベリア」と同時進行していたように、ドビュッシーのピアノ曲はオーケストラ曲やオペラ、声楽曲と密接なかかわりももつものが多い。従って、単にピアノ曲としての解釈にとどまるのではなく、背景となっているテキストや管弦楽の色彩感をとりいれなければ、片手落ちになるだろう。
ドビュッシーの「音響宇宙」にはペダルの使用が不可欠だが、彼の発想はしばしば管弦楽的で、幾重もの音響レベルを明確に弾きわけるタッチとペダリングが求められる。
東洋美術に深い関心をもち、また作品にもとりいれたドビュッシーは、作曲にあたってのモットーを「ものごとの半分まで言って想像力に接ぎ木させる」と表現している。すべてをさらけ出さず、深く静かに潜行させるその姿勢は、東洋人、とりわけ日本人の美意識にもっとも近い作曲家ということができよう。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
フランス近代の印象派を代表する作曲家。長音階・短音階以外の旋法と、機能和声にとらわれない自由な和声法などとを用いて独自の作曲を実行した。ドビュッシーの音楽は、その特徴的な和音構成などで、音の印象を表現するという独特の表現スタイルを確立し、「印象主義音楽(印象派)」と称されている。
演奏家解説 - 金田 真理子
日本のピアニスト。パリ国立高等音楽院をプルミエプリを取って卒業。マネス音楽院で修士号を、博士号をニューヨーク市立大学大学院で取得。
モントリオール国際ピアノコンクール、マリア・カナルス国際ピアノコンクールに入賞。国内外で交響楽団戸の共演、リサイタルを行う。また、室内楽奏者としても活発に活動。
2004年オハイオ・ウェズレヤン大学准教授に就任。ピティナ正会員。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より