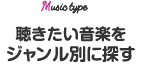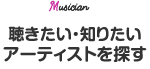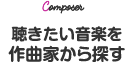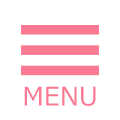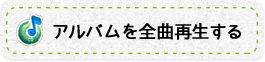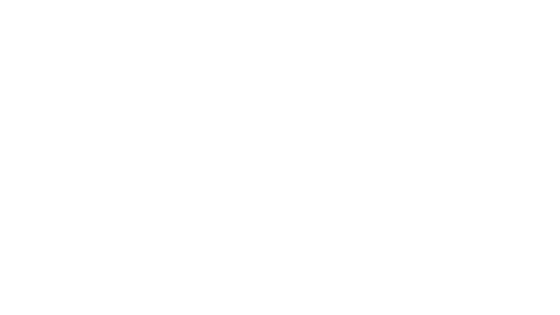![]()
ラヴェル 古風なメヌエット(Orc版) 動画集
ラヴェル 古風なメヌエット(オーケストラ版)の動画集です。

1. 古風なメヌエット (オーケストラ版) / ラヴェル,モーリス / アバド,クラウディオ
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 古風なメヌエット (オーケストラ版)
この『古風なるメヌエット』はラヴェルがまだパリ音楽院の学生だった1895年に作曲された、初期の作品である。タイトル通り、中間部にトリオの部分を置いた、古風なメヌエットの形式をそのまま用いている。メロディーも素朴で温かくロマンティックな特徴を備えるが、7や9の和音を多用してラヴェル特有の現代的、都会的な洗練された小品に仕上がっている。
冒頭の密集した和音による音型をテーマに用い、それを左手にも登場させるが、決して厚ぼったい混乱した響きにはならず、若いながらも巧みな作曲技法を見せる。中間部のトリオの部分では一転して穏やかなメロディーが流れるように登場するが、その終わり近くでは冒頭部の密集した和音の音型も挿入し、絶妙な効果を上げている。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
作曲家解説 - ラヴェル,モーリス
ドビュッシーと並び近代フランスを代表する作曲家。スペイン国境近くのバスク地方シブールに生まれる。母親はバスク人。パリ音楽院では(1889-1901)、ベリオにピアノを、ジェダルジュに対位法を、フォーレに作曲を学ぶ。 ローマ賞は二等が最高で、大賞を目指して受験を続けるものの、1905年には受験資格なしと判断される。この結果への抗議が殺到し、当時のパリ音楽院院長デュボワは、辞任に追い込まれる事態となった。1910年にはケクラン、カプレ、ロジェ・デュカスらと独立音楽協会(SMI)を立ち上げた。彼らは皆、ドビュッシーの音楽を尊敬し、その影響を受けた前衛たちだった。一方でラヴェルの音楽は、古いものにただ反抗するという性質のものではなく、古典やロマン派の音楽からも多くを学び、取り入れている。
各ジャンルに傑作を残しているが、バレエ音楽を中心とする管弦楽の分野でとりわけ突出した才能を発揮した。ピアノ作品にも管弦楽書法が応用されているため難曲が多いが、全ピアノ作品を聴くと、ラヴェルの音楽的インスピレーションを概観できる。 古典形式や舞曲(そしてリズム)への敬意、お伽話のような子供の世界、印象派/象徴派にも通じる自然や幻想世界の表現、そしてロシアやスペイン、東洋などの異国情緒。こうした彼の音楽は、ユーモア、洒脱さ、優雅さ、洗練といった、フランス音楽のイメージ通りの特徴の中にも、どこかしら哀愁が漂い、多くの人に愛され続ける独特の世界を作り上げている。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
演奏家解説 - アバド,クラウディオ
イタリア、ミラノ出身の指揮者。1990年からベルリン・フィルハーモニー管弦楽団芸術監督に就任し、名実共に現代最高の指揮者としての地位を確立した。
2. 古風なメヌエット (オーケストラ版) / ラヴェル,モーリス / モントリオール交響楽団
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 古風なメヌエット (オーケストラ版)
この『古風なるメヌエット』はラヴェルがまだパリ音楽院の学生だった1895年に作曲された、初期の作品である。タイトル通り、中間部にトリオの部分を置いた、古風なメヌエットの形式をそのまま用いている。メロディーも素朴で温かくロマンティックな特徴を備えるが、7や9の和音を多用してラヴェル特有の現代的、都会的な洗練された小品に仕上がっている。
冒頭の密集した和音による音型をテーマに用い、それを左手にも登場させるが、決して厚ぼったい混乱した響きにはならず、若いながらも巧みな作曲技法を見せる。中間部のトリオの部分では一転して穏やかなメロディーが流れるように登場するが、その終わり近くでは冒頭部の密集した和音の音型も挿入し、絶妙な効果を上げている。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
作曲家解説 - ラヴェル,モーリス
ドビュッシーと並び近代フランスを代表する作曲家。スペイン国境近くのバスク地方シブールに生まれる。母親はバスク人。パリ音楽院では(1889-1901)、ベリオにピアノを、ジェダルジュに対位法を、フォーレに作曲を学ぶ。 ローマ賞は二等が最高で、大賞を目指して受験を続けるものの、1905年には受験資格なしと判断される。この結果への抗議が殺到し、当時のパリ音楽院院長デュボワは、辞任に追い込まれる事態となった。1910年にはケクラン、カプレ、ロジェ・デュカスらと独立音楽協会(SMI)を立ち上げた。彼らは皆、ドビュッシーの音楽を尊敬し、その影響を受けた前衛たちだった。一方でラヴェルの音楽は、古いものにただ反抗するという性質のものではなく、古典やロマン派の音楽からも多くを学び、取り入れている。
各ジャンルに傑作を残しているが、バレエ音楽を中心とする管弦楽の分野でとりわけ突出した才能を発揮した。ピアノ作品にも管弦楽書法が応用されているため難曲が多いが、全ピアノ作品を聴くと、ラヴェルの音楽的インスピレーションを概観できる。 古典形式や舞曲(そしてリズム)への敬意、お伽話のような子供の世界、印象派/象徴派にも通じる自然や幻想世界の表現、そしてロシアやスペイン、東洋などの異国情緒。こうした彼の音楽は、ユーモア、洒脱さ、優雅さ、洗練といった、フランス音楽のイメージ通りの特徴の中にも、どこかしら哀愁が漂い、多くの人に愛され続ける独特の世界を作り上げている。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より