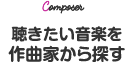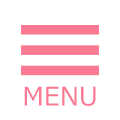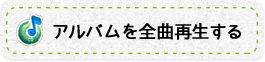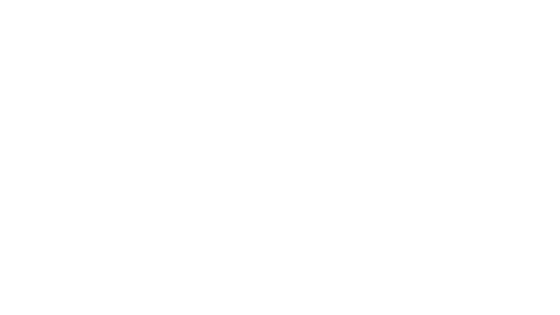![]()
リスト 巡礼の年3年 全曲動画集
リスト 巡礼の年第3年 全曲の動画集です。

リスト 巡礼の年 第3年 S.163
LISZT Années de pèlerinage Troisième année S.163
リストの巡礼の年第3年 全7曲です。
《巡礼の年》は第1年、第2年、第2年補巻、第3年の4集からなるピアノ独奏曲集です。
リスト 巡礼の年動画集一覧はこちら
1. 巡礼の年 第3年 全曲 / リスト,フランツ / ベルマン,ラザール
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 巡礼の年 第3年 全曲
《巡礼の年 第3年》は、同じ題名を持つ先の3つの曲集とは性格の異なる曲集である。創作年代にも間があり、リストの生涯における、いわゆるローマ時代(1861-69)に作曲が開始されている。リストはこの期間に充実した作曲活動を展開しており、その中でも宗教音楽への傾倒を見せている。本作品集の多くは1877年に作曲されている。それまでの経緯を簡単に述べると、1870年頃より、59歳のリストは季節ごとにヴァイマル、ブタペスト、ローマの3都市を住み分ける生活を送るようになる。1886年にリストが亡くなるまで続くこの生活は多忙を極め、しばらく創作活動が滞っている。ブタペストではハンガリー王立学院(今日のリスト音楽院)の学長を務め、自らも指導にあたっていた。だが、自らの作品が「芸術の否定である」と手ひどい批判を受けるなど、周囲からの理解を得られないことに対する諦めもあり、決して成功ばかりではなかった。1877年、66歳になるリストは精神的に深刻な状況に陥っている。この頃、知人のオルガ・フォン・マイエンドルフ男爵夫人(1838-1926)に宛てた手紙には、「絶望的な悲しみに襲われる」など、生きることへの苦しみが綴られている。
この曲集においては、レチタティーヴォを思わせる単音の長いパッセージや不協和音の使用が目立ち、作品の冒頭において調性が曖昧であることが目立つが、これは晩年のリストの様式を示している。宗教曲が3曲(第1番、4番、7番)あり、その他の作品も哀歌と題されるものがあり、華麗さは影を潜め、強い諦念すら感じられるものとなっている。
第1番「夕べの鐘、守護天使への祈り」 / No.1 "Angelus! Priere aux anges gardiens"。タイトルにある夕べの鐘(Angelus!)とは、朝、昼、晩の三度行なわれるお告げの祈り、またその時に鳴らされるお告げの鐘を意味している。このお告げとは受胎告知のこと。本作品は1877年より作曲が始められ、四回の改訂を経て、現在の形になった。関連する作品として、1882年に弦楽四重奏によるもの、及びハルモニウム(オルガン)によるもの(ともに1883年初版出版)がある。
第2番「エステ荘の糸杉に寄せて-葬送歌(第1)」 / No.2 "Aux cypres de la Villa d'Este - Threnodie I"、第3番「エステ荘の糸杉に寄せて-葬送歌(第2)」 / No.3 "Aux cypres de la Villa d'Este - Threnodie II"。タイトルにある「エステ荘」とは、エステ家出身の枢機卿イッポリト2世によって1550年に着工されたベネディクト派の修道院であった。その後、豪華な別荘と美しい庭園に改築された。豊富な水資源を生かし、「水オルガンの噴水」や「ドラゴンの噴水」など大小500の噴水が存在し、現在もティヴォリ随一の観光地として人気がある。リストはそのエステ荘に1868年よりグスターフ・フォン・ホーエンローエ枢機卿の客人として滞在していた。またタイトルにある「糸杉」は西洋において死や喪を象徴するものとして音楽に限らず、フィンセント・ファン・ゴッホのように絵画等でも多く扱われている。第2番「エステ荘の糸杉に寄せて-葬送歌(第1)」は、重々しい四度の連続から始まり、陰鬱な雰囲気に満ちた作品。第3番「エステ荘の糸杉に寄せて-葬送歌(第2)」も同様に力強いが陰鬱さを持った動機から始まり、途中ハンガリー風の旋律を経て、流麗な旋律へと姿を変える。
第4番「エステ荘の噴水」 / No.4 "Les jeux d'eaux a la Villa d'Este"。前に二曲に続いて、エステ荘に関する作品。リスト晩年の作品の中でも最も有名で演奏機会も極めて多い。水をあらわす繊細な動きと朗々とした旋律の明るい作品。曲の半ばには、ヨハネ福音書より引用された「わたしが与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る」(新共同訳より)との標題がある。
第5番「哀れならずや-ハンガリー風に」 / No.5 "Sunt lacrymae rerum"。原文のタイトルSunt lacrymae rerumはラテン語で、忠実に訳すと「人の世に注ぐ涙あり」となる。もともとは1848-49年に起きたハンガリーの革命の犠牲者へ捧げた《ハンガリー哀歌》という作品。現在の曲名は、古代ローマの詩人ヴェルギリウスの未完の大叙事詩『アエネーイス』の第一歌四六二行より採られている。前曲とは打って変わって、本作品は重さと暗さに満ちており、一部にハンガリー旋法が用いられている。
第6番「葬送行進曲」 / No.6 "Marche funebre"。1867年6月19 日に処刑されたメキシコ皇帝マクシミリアン1世の為に作曲された。ローマ時代にあたり、《ハンガリー戴冠式ミサ》の初演やリヒャルト・ヴァーグナーと絶縁のあった1867年に作曲。本作品集の中では最も早く作曲された曲である。
第7番「心を高めよ」(スルスム・コルダ) / No.7 "Sursum corda!"。作品のタイトルSursum cordaとは、ミサにおける叙唱の前に為される司教と会衆の応答の言葉。属音の静かな連打で始まる本作品は、全音音階(1オクターヴを全音で6等分する)が用いられている。曲名から想起されるように崇高な印象を与える作品である。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
作曲家解説 - リスト,フランツ
ハンガリー系のドイツのピアニスト、作曲家。本人はハンガリー語を母国語として解さずその文化も異質なものであったが、自らの血統を強く意識していた。ヨーロッパ中をその活動地とし、ドイツ語圏のほかはパリ、ローマで活躍した。
神童としてヴィーン、次いでパリにデビューした。若くして演奏家として名を挙げたリストは、しかし、いったん華やかな社交界を辞してスイスへ移り住み、自らの音楽性を探求する日々を送る。これが《旅人のアルバム》、《巡礼の年報》に実を結んだ。また、39年にイタリアで表舞台に復帰した後に《ダンテを読んで》《ペトラルカのソネット》などが生まれるのも、その延長上の成果である。
その後の8年間でリストは、ヴィルトゥオーゾとしてヨーロッパ全土に熱狂を巻き起こした。が、演奏旅行に明け暮れる生活をやめ、作曲に専念することを決意する。1848年、ヴァイマル宮廷楽団の常任指揮者となり、居を構えた。ここでリストは、自らの管弦楽曲、とりわけ交響詩と標題交響曲のための実験を繰り返し、大規模作品を完成させていく。また鍵盤作品にも《超絶技巧練習曲》、ピアノ・ソナタロ短調などがある。 しかし53年にヴァイマル大公が代替わりすると、61年にはローマへ赴いた。
やがてまた、69年にはヴァイマルでピアノの教授活動を再開、のちにブダペストでもピアノのレッスンをうけもち、ローマと併せて3つの都市を行き来する生活となった。晩年は彼のもとを訪れた多くの音楽家を温かく励まし、優れた弟子を世に送り出した。生涯を通じて音楽の未来を信じ、つねに音楽の歴史の「前衛」であろうとした。
リストが音楽史上最大の技術を持つピアニストであったことは、彼が「自分のために」作曲した数々の難曲と、当時の演奏会評から確かめられよう。また、レパートリーもきわめて広範囲に及び、当時はまだ決して一般に広まっていたとはいえないバッハの対位法作品から、音楽的に対立する党派といわれたシューマンの作品まで、ありとあらゆるものを取り上げた。更にリストは、従来さまざまなジャンルや編成と複数の出演者で行っていた公開演奏会の形式を改め、自分ひとりで弾きとおすリサイタルを始め、集中力のより高い演奏会を作り出した。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
演奏家解説 - ベルマン,ラザール
旧ソ連出身のロシア人ピアニスト。日本では慣習的に「ラザール」とフランス語風に表記されているが、ロシア語の発音では第一音節に強勢が置かれるため「ラーザリ」が近い。
「私は19世紀の人間であり、ヴィルトゥオーソと呼ばれるタイプの演奏家に属している」と自認していたように、鮮やかな超絶技巧と芝居っ気たっぷりの演奏、濃やかな情緒表現と強靭なタッチが特徴的で、一夜で3つのピアノ協奏曲とソナタ1曲を弾き切ったこともある。
2. 巡礼の年 第3年 全曲 / リスト,フランツ / チッコリーニ,アルド
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 巡礼の年 第3年 全曲
《巡礼の年 第3年》は、同じ題名を持つ先の3つの曲集とは性格の異なる曲集である。創作年代にも間があり、リストの生涯における、いわゆるローマ時代(1861-69)に作曲が開始されている。リストはこの期間に充実した作曲活動を展開しており、その中でも宗教音楽への傾倒を見せている。本作品集の多くは1877年に作曲されている。それまでの経緯を簡単に述べると、1870年頃より、59歳のリストは季節ごとにヴァイマル、ブタペスト、ローマの3都市を住み分ける生活を送るようになる。1886年にリストが亡くなるまで続くこの生活は多忙を極め、しばらく創作活動が滞っている。ブタペストではハンガリー王立学院(今日のリスト音楽院)の学長を務め、自らも指導にあたっていた。だが、自らの作品が「芸術の否定である」と手ひどい批判を受けるなど、周囲からの理解を得られないことに対する諦めもあり、決して成功ばかりではなかった。1877年、66歳になるリストは精神的に深刻な状況に陥っている。この頃、知人のオルガ・フォン・マイエンドルフ男爵夫人(1838-1926)に宛てた手紙には、「絶望的な悲しみに襲われる」など、生きることへの苦しみが綴られている。
この曲集においては、レチタティーヴォを思わせる単音の長いパッセージや不協和音の使用が目立ち、作品の冒頭において調性が曖昧であることが目立つが、これは晩年のリストの様式を示している。宗教曲が3曲(第1番、4番、7番)あり、その他の作品も哀歌と題されるものがあり、華麗さは影を潜め、強い諦念すら感じられるものとなっている。
第1番「夕べの鐘、守護天使への祈り」 / No.1 "Angelus! Priere aux anges gardiens"。タイトルにある夕べの鐘(Angelus!)とは、朝、昼、晩の三度行なわれるお告げの祈り、またその時に鳴らされるお告げの鐘を意味している。このお告げとは受胎告知のこと。本作品は1877年より作曲が始められ、四回の改訂を経て、現在の形になった。関連する作品として、1882年に弦楽四重奏によるもの、及びハルモニウム(オルガン)によるもの(ともに1883年初版出版)がある。
第2番「エステ荘の糸杉に寄せて-葬送歌(第1)」 / No.2 "Aux cypres de la Villa d'Este - Threnodie I"、第3番「エステ荘の糸杉に寄せて-葬送歌(第2)」 / No.3 "Aux cypres de la Villa d'Este - Threnodie II"。タイトルにある「エステ荘」とは、エステ家出身の枢機卿イッポリト2世によって1550年に着工されたベネディクト派の修道院であった。その後、豪華な別荘と美しい庭園に改築された。豊富な水資源を生かし、「水オルガンの噴水」や「ドラゴンの噴水」など大小500の噴水が存在し、現在もティヴォリ随一の観光地として人気がある。リストはそのエステ荘に1868年よりグスターフ・フォン・ホーエンローエ枢機卿の客人として滞在していた。またタイトルにある「糸杉」は西洋において死や喪を象徴するものとして音楽に限らず、フィンセント・ファン・ゴッホのように絵画等でも多く扱われている。第2番「エステ荘の糸杉に寄せて-葬送歌(第1)」は、重々しい四度の連続から始まり、陰鬱な雰囲気に満ちた作品。第3番「エステ荘の糸杉に寄せて-葬送歌(第2)」も同様に力強いが陰鬱さを持った動機から始まり、途中ハンガリー風の旋律を経て、流麗な旋律へと姿を変える。
第4番「エステ荘の噴水」 / No.4 "Les jeux d'eaux a la Villa d'Este"。前に二曲に続いて、エステ荘に関する作品。リスト晩年の作品の中でも最も有名で演奏機会も極めて多い。水をあらわす繊細な動きと朗々とした旋律の明るい作品。曲の半ばには、ヨハネ福音書より引用された「わたしが与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る」(新共同訳より)との標題がある。
第5番「哀れならずや-ハンガリー風に」 / No.5 "Sunt lacrymae rerum"。原文のタイトルSunt lacrymae rerumはラテン語で、忠実に訳すと「人の世に注ぐ涙あり」となる。もともとは1848-49年に起きたハンガリーの革命の犠牲者へ捧げた《ハンガリー哀歌》という作品。現在の曲名は、古代ローマの詩人ヴェルギリウスの未完の大叙事詩『アエネーイス』の第一歌四六二行より採られている。前曲とは打って変わって、本作品は重さと暗さに満ちており、一部にハンガリー旋法が用いられている。
第6番「葬送行進曲」 / No.6 "Marche funebre"。1867年6月19 日に処刑されたメキシコ皇帝マクシミリアン1世の為に作曲された。ローマ時代にあたり、《ハンガリー戴冠式ミサ》の初演やリヒャルト・ヴァーグナーと絶縁のあった1867年に作曲。本作品集の中では最も早く作曲された曲である。
第7番「心を高めよ」(スルスム・コルダ) / No.7 "Sursum corda!"。作品のタイトルSursum cordaとは、ミサにおける叙唱の前に為される司教と会衆の応答の言葉。属音の静かな連打で始まる本作品は、全音音階(1オクターヴを全音で6等分する)が用いられている。曲名から想起されるように崇高な印象を与える作品である。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
作曲家解説 - リスト,フランツ
ハンガリー系のドイツのピアニスト、作曲家。本人はハンガリー語を母国語として解さずその文化も異質なものであったが、自らの血統を強く意識していた。ヨーロッパ中をその活動地とし、ドイツ語圏のほかはパリ、ローマで活躍した。
神童としてヴィーン、次いでパリにデビューした。若くして演奏家として名を挙げたリストは、しかし、いったん華やかな社交界を辞してスイスへ移り住み、自らの音楽性を探求する日々を送る。これが《旅人のアルバム》、《巡礼の年報》に実を結んだ。また、39年にイタリアで表舞台に復帰した後に《ダンテを読んで》《ペトラルカのソネット》などが生まれるのも、その延長上の成果である。
その後の8年間でリストは、ヴィルトゥオーゾとしてヨーロッパ全土に熱狂を巻き起こした。が、演奏旅行に明け暮れる生活をやめ、作曲に専念することを決意する。1848年、ヴァイマル宮廷楽団の常任指揮者となり、居を構えた。ここでリストは、自らの管弦楽曲、とりわけ交響詩と標題交響曲のための実験を繰り返し、大規模作品を完成させていく。また鍵盤作品にも《超絶技巧練習曲》、ピアノ・ソナタロ短調などがある。 しかし53年にヴァイマル大公が代替わりすると、61年にはローマへ赴いた。
やがてまた、69年にはヴァイマルでピアノの教授活動を再開、のちにブダペストでもピアノのレッスンをうけもち、ローマと併せて3つの都市を行き来する生活となった。晩年は彼のもとを訪れた多くの音楽家を温かく励まし、優れた弟子を世に送り出した。生涯を通じて音楽の未来を信じ、つねに音楽の歴史の「前衛」であろうとした。
リストが音楽史上最大の技術を持つピアニストであったことは、彼が「自分のために」作曲した数々の難曲と、当時の演奏会評から確かめられよう。また、レパートリーもきわめて広範囲に及び、当時はまだ決して一般に広まっていたとはいえないバッハの対位法作品から、音楽的に対立する党派といわれたシューマンの作品まで、ありとあらゆるものを取り上げた。更にリストは、従来さまざまなジャンルや編成と複数の出演者で行っていた公開演奏会の形式を改め、自分ひとりで弾きとおすリサイタルを始め、集中力のより高い演奏会を作り出した。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
演奏家解説 - チッコリーニ,アルド
フランス在住のイタリア人ピアニスト。ナポリ出身。1949年にパリのロン・ティボー国際コンクールに優勝する。1969年にフランスに帰化し、1970年から1983年までパリ音楽院で教鞭を執った。フランス近代音楽の解釈者ならびに擁護者として国際的に著名であり、数多くの曲を録音している。