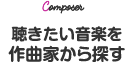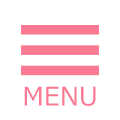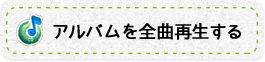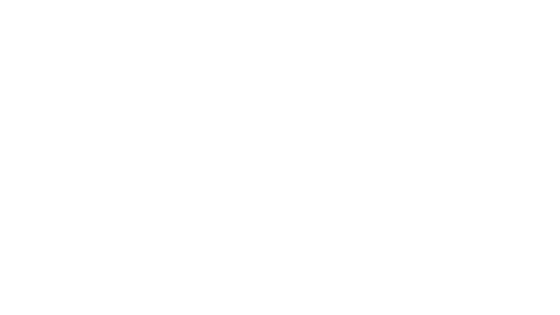![]()
ドビュッシー 練習曲集XI.組み合わされたアルペッジョの為に 動画集
ドビュッシー 練習曲集XI組み合わされたアルペッジョのために動画集です。

ドビュッシー 練習曲集
第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲 L136-11
DEBUSSY Etudes
XI. Pour les arpeges composes L136-11
ドビュッシー 練習曲集の第11曲組み合わされたアルペッジョのためにです。
ドビュッシーが最晩年に作曲した全12曲の作品集です。
ドビュッシー 練習曲集動画集一覧はこちら
- アルバム収録曲
- 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲 / ドビュッシー,クロード / 金子 一朗
- 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲 / ドビュッシー,クロード / 金平 泰介
- 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲 / ドビュッシー,クロード / クズネツォフ,セルゲイ
- 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲 / ドビュッシー,クロード / ベロフ,ミッシェル
- 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲 / ドビュッシー,クロード / テオドーレ・パラスキヴェスコ
- 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲 / ドビュッシー,クロード / チッコリーニ,アルド
- 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲 / ドビュッシー,クロード / 内田 光子
1. 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲 / ドビュッシー,クロード / 金子 一朗
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲
1915年、これまで健康の不調と第一次大戦への苦悩などからしばらく作曲ができていなかったドビュッシーだが、ショパンの楽譜を校訂する仕事をきっかけに、創作力をとりもどした。ここで作曲されたのが《12の練習曲》であり、これはショパンに献呈されている。この練習曲では、ただ技巧を追求するための作品として作曲されているわけではない。彼はこの作品を通じて、彼自身の音楽性のあり方を再検討したのであろう。練習曲でありながら、運指法が指示されていないことも特徴の一つであるが、ドビュッシーはこれを意図的におこなっている。つまり、演奏者の腕や手の構造には違いがあるため、各人に合った運指法を各自で追求していくこともまた、課題の一つになっているのである。
6曲ずつの2巻に分けられている。
11.組み合わされたアルペッジョのための / "Pour les arpeges composes"。この作品には曲想表示がない。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
ドビュッシーの旋律や和声に関する才能をよく示している。主要なテーマは、彩られて輝く一連の音符によって曲全体を通じて巧みに移動する。ドビュッシーはいつも安易な旋律を避け、聞き手を思いがけない音の世界へ誘うことを望んだ。
作曲家解説 - ドビュッシー,クロード
フランスの作曲家。
クロード・アシル・ドビュッシーは1862年8月22日、父マニュエルと母ヴィクトリーヌの長男として、パリ西郊約20キロの町サン=ジェルマン=アン=レに生まれた。
ドビュッシーは、ワーグナーを乗り越えるためにフランス固有の美を武器とし、大胆な語法によって20世紀音楽への扉をあけた作曲家である。長調・短調の明確な対比を嫌った彼は、教会旋法、東洋風の5音音階、全音音階などを駆使し、印象派の画家たちが遠近法を回避するために画面を分割したように、平面的、スタティックな美を生み出した。
ドビュッシーのピアニズムには、大きくわけて次の3つの源流がある。モーテ夫人を通じて伝えられたショパンの技法(ビロードのようなタッチと美しい響き、軽やかなリズムなど)、やはりモーテ夫人に目を開かれたバッハの書法(対位法的、優雅なアラベスクなど)、18世紀クラヴサン音楽の技法(多彩な装飾音、「バトリ」など)。
ドビュッシー独自の語法としては、ペダルで白鍵と黒鍵の響きを混ぜたり、重音や和音塊を平行移動させたり、いくつもの層を積み重ねて、独特の「音響宇宙」を生み出したこと、ポリリズムやルバートを多用して自在な律動を作り出したことなどがあげられる。
1907年にドビュッシーは、「私はますます音楽というのは色彩と律動づけられた時間でできていると確信するようになった」と書いているが、調性からもリズムからも自由になりながら有機性を失わなかったドビュッシーの在り方を象徴するような言葉である。
『前奏曲集第1巻』が『管弦楽のための映像』の「イベリア」と同時進行していたように、ドビュッシーのピアノ曲はオーケストラ曲やオペラ、声楽曲と密接なかかわりももつものが多い。従って、単にピアノ曲としての解釈にとどまるのではなく、背景となっているテキストや管弦楽の色彩感をとりいれなければ、片手落ちになるだろう。
ドビュッシーの「音響宇宙」にはペダルの使用が不可欠だが、彼の発想はしばしば管弦楽的で、幾重もの音響レベルを明確に弾きわけるタッチとペダリングが求められる。
東洋美術に深い関心をもち、また作品にもとりいれたドビュッシーは、作曲にあたってのモットーを「ものごとの半分まで言って想像力に接ぎ木させる」と表現している。すべてをさらけ出さず、深く静かに潜行させるその姿勢は、東洋人、とりわけ日本人の美意識にもっとも近い作曲家ということができよう。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
フランス近代の印象派を代表する作曲家。長音階・短音階以外の旋法と、機能和声にとらわれない自由な和声法などとを用いて独自の作曲を実行した。ドビュッシーの音楽は、その特徴的な和音構成などで、音の印象を表現するという独特の表現スタイルを確立し、「印象主義音楽(印象派)」と称されている。
演奏家解説 - 金子 一朗
日本のピアニスト。早稲田大学理工学部数学科卒。本職は中・高等学校の数学科教諭。ピティナピアノコンペティション ソロ部門特級は2003~4年ともに入選、コンチェルト部門上級で2004年に奨励賞、グランミューズ部門A1カテゴリーで2004年に第1位受賞、2005年ソロ部門特級でグランプリ(金賞)および聴衆賞、ミキモト賞、王子賞、日フィル賞、文部科学大臣賞、読売新聞社賞、審査員基金海外派遣費用補助を受賞。2007年3月、『ピティナ40周年記念 ピアノコンチェルトの夕べ』にて渡邊一正指揮・NHK交響楽団と共演。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
2. 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲 / ドビュッシー,クロード / 金平 泰介
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲
1915年、これまで健康の不調と第一次大戦への苦悩などからしばらく作曲ができていなかったドビュッシーだが、ショパンの楽譜を校訂する仕事をきっかけに、創作力をとりもどした。ここで作曲されたのが《12の練習曲》であり、これはショパンに献呈されている。この練習曲では、ただ技巧を追求するための作品として作曲されているわけではない。彼はこの作品を通じて、彼自身の音楽性のあり方を再検討したのであろう。練習曲でありながら、運指法が指示されていないことも特徴の一つであるが、ドビュッシーはこれを意図的におこなっている。つまり、演奏者の腕や手の構造には違いがあるため、各人に合った運指法を各自で追求していくこともまた、課題の一つになっているのである。
6曲ずつの2巻に分けられている。
11.組み合わされたアルペッジョのための / "Pour les arpeges composes"。この作品には曲想表示がない。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
ドビュッシーの旋律や和声に関する才能をよく示している。主要なテーマは、彩られて輝く一連の音符によって曲全体を通じて巧みに移動する。ドビュッシーはいつも安易な旋律を避け、聞き手を思いがけない音の世界へ誘うことを望んだ。
作曲家解説 - ドビュッシー,クロード
フランスの作曲家。
クロード・アシル・ドビュッシーは1862年8月22日、父マニュエルと母ヴィクトリーヌの長男として、パリ西郊約20キロの町サン=ジェルマン=アン=レに生まれた。
ドビュッシーは、ワーグナーを乗り越えるためにフランス固有の美を武器とし、大胆な語法によって20世紀音楽への扉をあけた作曲家である。長調・短調の明確な対比を嫌った彼は、教会旋法、東洋風の5音音階、全音音階などを駆使し、印象派の画家たちが遠近法を回避するために画面を分割したように、平面的、スタティックな美を生み出した。
ドビュッシーのピアニズムには、大きくわけて次の3つの源流がある。モーテ夫人を通じて伝えられたショパンの技法(ビロードのようなタッチと美しい響き、軽やかなリズムなど)、やはりモーテ夫人に目を開かれたバッハの書法(対位法的、優雅なアラベスクなど)、18世紀クラヴサン音楽の技法(多彩な装飾音、「バトリ」など)。
ドビュッシー独自の語法としては、ペダルで白鍵と黒鍵の響きを混ぜたり、重音や和音塊を平行移動させたり、いくつもの層を積み重ねて、独特の「音響宇宙」を生み出したこと、ポリリズムやルバートを多用して自在な律動を作り出したことなどがあげられる。
1907年にドビュッシーは、「私はますます音楽というのは色彩と律動づけられた時間でできていると確信するようになった」と書いているが、調性からもリズムからも自由になりながら有機性を失わなかったドビュッシーの在り方を象徴するような言葉である。
『前奏曲集第1巻』が『管弦楽のための映像』の「イベリア」と同時進行していたように、ドビュッシーのピアノ曲はオーケストラ曲やオペラ、声楽曲と密接なかかわりももつものが多い。従って、単にピアノ曲としての解釈にとどまるのではなく、背景となっているテキストや管弦楽の色彩感をとりいれなければ、片手落ちになるだろう。
ドビュッシーの「音響宇宙」にはペダルの使用が不可欠だが、彼の発想はしばしば管弦楽的で、幾重もの音響レベルを明確に弾きわけるタッチとペダリングが求められる。
東洋美術に深い関心をもち、また作品にもとりいれたドビュッシーは、作曲にあたってのモットーを「ものごとの半分まで言って想像力に接ぎ木させる」と表現している。すべてをさらけ出さず、深く静かに潜行させるその姿勢は、東洋人、とりわけ日本人の美意識にもっとも近い作曲家ということができよう。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
フランス近代の印象派を代表する作曲家。長音階・短音階以外の旋法と、機能和声にとらわれない自由な和声法などとを用いて独自の作曲を実行した。ドビュッシーの音楽は、その特徴的な和音構成などで、音の印象を表現するという独特の表現スタイルを確立し、「印象主義音楽(印象派)」と称されている。
演奏家解説 - 金平 泰介
日本のピアニスト。1996年渡仏。サン・ノン・ラ・ブルテッシュ国際ピアノコンクール(フランス)第2位入賞。2000年、2001年、リスト国際ピアノコンクール(イタリア)、仙台国際ピアノコンクール セミファイナリスト。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
3. 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲 / ドビュッシー,クロード / クズネツォフ,セルゲイ
若手演奏家なので、解釈には、多少個人的な好みが入っていて、オーソドックスではないですが、勢いがある演奏です。
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲
1915年、これまで健康の不調と第一次大戦への苦悩などからしばらく作曲ができていなかったドビュッシーだが、ショパンの楽譜を校訂する仕事をきっかけに、創作力をとりもどした。ここで作曲されたのが《12の練習曲》であり、これはショパンに献呈されている。この練習曲では、ただ技巧を追求するための作品として作曲されているわけではない。彼はこの作品を通じて、彼自身の音楽性のあり方を再検討したのであろう。練習曲でありながら、運指法が指示されていないことも特徴の一つであるが、ドビュッシーはこれを意図的におこなっている。つまり、演奏者の腕や手の構造には違いがあるため、各人に合った運指法を各自で追求していくこともまた、課題の一つになっているのである。
6曲ずつの2巻に分けられている。
11.組み合わされたアルペッジョのための / "Pour les arpeges composes"。この作品には曲想表示がない。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
ドビュッシーの旋律や和声に関する才能をよく示している。主要なテーマは、彩られて輝く一連の音符によって曲全体を通じて巧みに移動する。ドビュッシーはいつも安易な旋律を避け、聞き手を思いがけない音の世界へ誘うことを望んだ。
作曲家解説 - ドビュッシー,クロード
フランスの作曲家。
クロード・アシル・ドビュッシーは1862年8月22日、父マニュエルと母ヴィクトリーヌの長男として、パリ西郊約20キロの町サン=ジェルマン=アン=レに生まれた。
ドビュッシーは、ワーグナーを乗り越えるためにフランス固有の美を武器とし、大胆な語法によって20世紀音楽への扉をあけた作曲家である。長調・短調の明確な対比を嫌った彼は、教会旋法、東洋風の5音音階、全音音階などを駆使し、印象派の画家たちが遠近法を回避するために画面を分割したように、平面的、スタティックな美を生み出した。
ドビュッシーのピアニズムには、大きくわけて次の3つの源流がある。モーテ夫人を通じて伝えられたショパンの技法(ビロードのようなタッチと美しい響き、軽やかなリズムなど)、やはりモーテ夫人に目を開かれたバッハの書法(対位法的、優雅なアラベスクなど)、18世紀クラヴサン音楽の技法(多彩な装飾音、「バトリ」など)。
ドビュッシー独自の語法としては、ペダルで白鍵と黒鍵の響きを混ぜたり、重音や和音塊を平行移動させたり、いくつもの層を積み重ねて、独特の「音響宇宙」を生み出したこと、ポリリズムやルバートを多用して自在な律動を作り出したことなどがあげられる。
1907年にドビュッシーは、「私はますます音楽というのは色彩と律動づけられた時間でできていると確信するようになった」と書いているが、調性からもリズムからも自由になりながら有機性を失わなかったドビュッシーの在り方を象徴するような言葉である。
『前奏曲集第1巻』が『管弦楽のための映像』の「イベリア」と同時進行していたように、ドビュッシーのピアノ曲はオーケストラ曲やオペラ、声楽曲と密接なかかわりももつものが多い。従って、単にピアノ曲としての解釈にとどまるのではなく、背景となっているテキストや管弦楽の色彩感をとりいれなければ、片手落ちになるだろう。
ドビュッシーの「音響宇宙」にはペダルの使用が不可欠だが、彼の発想はしばしば管弦楽的で、幾重もの音響レベルを明確に弾きわけるタッチとペダリングが求められる。
東洋美術に深い関心をもち、また作品にもとりいれたドビュッシーは、作曲にあたってのモットーを「ものごとの半分まで言って想像力に接ぎ木させる」と表現している。すべてをさらけ出さず、深く静かに潜行させるその姿勢は、東洋人、とりわけ日本人の美意識にもっとも近い作曲家ということができよう。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
フランス近代の印象派を代表する作曲家。長音階・短音階以外の旋法と、機能和声にとらわれない自由な和声法などとを用いて独自の作曲を実行した。ドビュッシーの音楽は、その特徴的な和音構成などで、音の印象を表現するという独特の表現スタイルを確立し、「印象主義音楽(印象派)」と称されている。
演奏家解説 - クズネツォフ,セルゲイ
ロシア,モスクワ出身。モスクワ音楽院卒。V. アリストヴァ,M. ボスクレセンスキー,O. マイセンバーグに師事。1999年A.M.A. カラブリア国際ピアノコンクール第1位,2003年ゲザ・アンダ国際ピアノコンクール 第2位, パブリック賞,2005年クリーヴランド国際ピアノコンクール第2位受賞。
4. 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲 / ドビュッシー,クロード / ベロフ,ミッシェル
1974年スタジオレコーディング
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲
1915年、これまで健康の不調と第一次大戦への苦悩などからしばらく作曲ができていなかったドビュッシーだが、ショパンの楽譜を校訂する仕事をきっかけに、創作力をとりもどした。ここで作曲されたのが《12の練習曲》であり、これはショパンに献呈されている。この練習曲では、ただ技巧を追求するための作品として作曲されているわけではない。彼はこの作品を通じて、彼自身の音楽性のあり方を再検討したのであろう。練習曲でありながら、運指法が指示されていないことも特徴の一つであるが、ドビュッシーはこれを意図的におこなっている。つまり、演奏者の腕や手の構造には違いがあるため、各人に合った運指法を各自で追求していくこともまた、課題の一つになっているのである。
6曲ずつの2巻に分けられている。
11.組み合わされたアルペッジョのための / "Pour les arpeges composes"。この作品には曲想表示がない。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
ドビュッシーの旋律や和声に関する才能をよく示している。主要なテーマは、彩られて輝く一連の音符によって曲全体を通じて巧みに移動する。ドビュッシーはいつも安易な旋律を避け、聞き手を思いがけない音の世界へ誘うことを望んだ。
作曲家解説 - ドビュッシー,クロード
フランスの作曲家。
クロード・アシル・ドビュッシーは1862年8月22日、父マニュエルと母ヴィクトリーヌの長男として、パリ西郊約20キロの町サン=ジェルマン=アン=レに生まれた。
ドビュッシーは、ワーグナーを乗り越えるためにフランス固有の美を武器とし、大胆な語法によって20世紀音楽への扉をあけた作曲家である。長調・短調の明確な対比を嫌った彼は、教会旋法、東洋風の5音音階、全音音階などを駆使し、印象派の画家たちが遠近法を回避するために画面を分割したように、平面的、スタティックな美を生み出した。
ドビュッシーのピアニズムには、大きくわけて次の3つの源流がある。モーテ夫人を通じて伝えられたショパンの技法(ビロードのようなタッチと美しい響き、軽やかなリズムなど)、やはりモーテ夫人に目を開かれたバッハの書法(対位法的、優雅なアラベスクなど)、18世紀クラヴサン音楽の技法(多彩な装飾音、「バトリ」など)。
ドビュッシー独自の語法としては、ペダルで白鍵と黒鍵の響きを混ぜたり、重音や和音塊を平行移動させたり、いくつもの層を積み重ねて、独特の「音響宇宙」を生み出したこと、ポリリズムやルバートを多用して自在な律動を作り出したことなどがあげられる。
1907年にドビュッシーは、「私はますます音楽というのは色彩と律動づけられた時間でできていると確信するようになった」と書いているが、調性からもリズムからも自由になりながら有機性を失わなかったドビュッシーの在り方を象徴するような言葉である。
『前奏曲集第1巻』が『管弦楽のための映像』の「イベリア」と同時進行していたように、ドビュッシーのピアノ曲はオーケストラ曲やオペラ、声楽曲と密接なかかわりももつものが多い。従って、単にピアノ曲としての解釈にとどまるのではなく、背景となっているテキストや管弦楽の色彩感をとりいれなければ、片手落ちになるだろう。
ドビュッシーの「音響宇宙」にはペダルの使用が不可欠だが、彼の発想はしばしば管弦楽的で、幾重もの音響レベルを明確に弾きわけるタッチとペダリングが求められる。
東洋美術に深い関心をもち、また作品にもとりいれたドビュッシーは、作曲にあたってのモットーを「ものごとの半分まで言って想像力に接ぎ木させる」と表現している。すべてをさらけ出さず、深く静かに潜行させるその姿勢は、東洋人、とりわけ日本人の美意識にもっとも近い作曲家ということができよう。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
フランス近代の印象派を代表する作曲家。長音階・短音階以外の旋法と、機能和声にとらわれない自由な和声法などとを用いて独自の作曲を実行した。ドビュッシーの音楽は、その特徴的な和音構成などで、音の印象を表現するという独特の表現スタイルを確立し、「印象主義音楽(印象派)」と称されている。
演奏家解説 - ベロフ,ミッシェル
フランスのピアニスト。
5. 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲 / ドビュッシー,クロード / テオドーレ・パラスキヴェスコ
1976年スタジオレコーディング
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲
1915年、これまで健康の不調と第一次大戦への苦悩などからしばらく作曲ができていなかったドビュッシーだが、ショパンの楽譜を校訂する仕事をきっかけに、創作力をとりもどした。ここで作曲されたのが《12の練習曲》であり、これはショパンに献呈されている。この練習曲では、ただ技巧を追求するための作品として作曲されているわけではない。彼はこの作品を通じて、彼自身の音楽性のあり方を再検討したのであろう。練習曲でありながら、運指法が指示されていないことも特徴の一つであるが、ドビュッシーはこれを意図的におこなっている。つまり、演奏者の腕や手の構造には違いがあるため、各人に合った運指法を各自で追求していくこともまた、課題の一つになっているのである。
6曲ずつの2巻に分けられている。
11.組み合わされたアルペッジョのための / "Pour les arpeges composes"。この作品には曲想表示がない。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
ドビュッシーの旋律や和声に関する才能をよく示している。主要なテーマは、彩られて輝く一連の音符によって曲全体を通じて巧みに移動する。ドビュッシーはいつも安易な旋律を避け、聞き手を思いがけない音の世界へ誘うことを望んだ。
作曲家解説 - ドビュッシー,クロード
フランスの作曲家。
クロード・アシル・ドビュッシーは1862年8月22日、父マニュエルと母ヴィクトリーヌの長男として、パリ西郊約20キロの町サン=ジェルマン=アン=レに生まれた。
ドビュッシーは、ワーグナーを乗り越えるためにフランス固有の美を武器とし、大胆な語法によって20世紀音楽への扉をあけた作曲家である。長調・短調の明確な対比を嫌った彼は、教会旋法、東洋風の5音音階、全音音階などを駆使し、印象派の画家たちが遠近法を回避するために画面を分割したように、平面的、スタティックな美を生み出した。
ドビュッシーのピアニズムには、大きくわけて次の3つの源流がある。モーテ夫人を通じて伝えられたショパンの技法(ビロードのようなタッチと美しい響き、軽やかなリズムなど)、やはりモーテ夫人に目を開かれたバッハの書法(対位法的、優雅なアラベスクなど)、18世紀クラヴサン音楽の技法(多彩な装飾音、「バトリ」など)。
ドビュッシー独自の語法としては、ペダルで白鍵と黒鍵の響きを混ぜたり、重音や和音塊を平行移動させたり、いくつもの層を積み重ねて、独特の「音響宇宙」を生み出したこと、ポリリズムやルバートを多用して自在な律動を作り出したことなどがあげられる。
1907年にドビュッシーは、「私はますます音楽というのは色彩と律動づけられた時間でできていると確信するようになった」と書いているが、調性からもリズムからも自由になりながら有機性を失わなかったドビュッシーの在り方を象徴するような言葉である。
『前奏曲集第1巻』が『管弦楽のための映像』の「イベリア」と同時進行していたように、ドビュッシーのピアノ曲はオーケストラ曲やオペラ、声楽曲と密接なかかわりももつものが多い。従って、単にピアノ曲としての解釈にとどまるのではなく、背景となっているテキストや管弦楽の色彩感をとりいれなければ、片手落ちになるだろう。
ドビュッシーの「音響宇宙」にはペダルの使用が不可欠だが、彼の発想はしばしば管弦楽的で、幾重もの音響レベルを明確に弾きわけるタッチとペダリングが求められる。
東洋美術に深い関心をもち、また作品にもとりいれたドビュッシーは、作曲にあたってのモットーを「ものごとの半分まで言って想像力に接ぎ木させる」と表現している。すべてをさらけ出さず、深く静かに潜行させるその姿勢は、東洋人、とりわけ日本人の美意識にもっとも近い作曲家ということができよう。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
フランス近代の印象派を代表する作曲家。長音階・短音階以外の旋法と、機能和声にとらわれない自由な和声法などとを用いて独自の作曲を実行した。ドビュッシーの音楽は、その特徴的な和音構成などで、音の印象を表現するという独特の表現スタイルを確立し、「印象主義音楽(印象派)」と称されている。
演奏家解説 - テオドーレ・パラスキヴェスコ
ルーマニア生まれ。フランスに帰化した。フランク人作曲家の演奏をよく手がけている。
6. 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲 / ドビュッシー,クロード / チッコリーニ,アルド
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲
1915年、これまで健康の不調と第一次大戦への苦悩などからしばらく作曲ができていなかったドビュッシーだが、ショパンの楽譜を校訂する仕事をきっかけに、創作力をとりもどした。ここで作曲されたのが《12の練習曲》であり、これはショパンに献呈されている。この練習曲では、ただ技巧を追求するための作品として作曲されているわけではない。彼はこの作品を通じて、彼自身の音楽性のあり方を再検討したのであろう。練習曲でありながら、運指法が指示されていないことも特徴の一つであるが、ドビュッシーはこれを意図的におこなっている。つまり、演奏者の腕や手の構造には違いがあるため、各人に合った運指法を各自で追求していくこともまた、課題の一つになっているのである。
6曲ずつの2巻に分けられている。
11.組み合わされたアルペッジョのための / "Pour les arpeges composes"。この作品には曲想表示がない。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
ドビュッシーの旋律や和声に関する才能をよく示している。主要なテーマは、彩られて輝く一連の音符によって曲全体を通じて巧みに移動する。ドビュッシーはいつも安易な旋律を避け、聞き手を思いがけない音の世界へ誘うことを望んだ。
作曲家解説 - ドビュッシー,クロード
フランスの作曲家。
クロード・アシル・ドビュッシーは1862年8月22日、父マニュエルと母ヴィクトリーヌの長男として、パリ西郊約20キロの町サン=ジェルマン=アン=レに生まれた。
ドビュッシーは、ワーグナーを乗り越えるためにフランス固有の美を武器とし、大胆な語法によって20世紀音楽への扉をあけた作曲家である。長調・短調の明確な対比を嫌った彼は、教会旋法、東洋風の5音音階、全音音階などを駆使し、印象派の画家たちが遠近法を回避するために画面を分割したように、平面的、スタティックな美を生み出した。
ドビュッシーのピアニズムには、大きくわけて次の3つの源流がある。モーテ夫人を通じて伝えられたショパンの技法(ビロードのようなタッチと美しい響き、軽やかなリズムなど)、やはりモーテ夫人に目を開かれたバッハの書法(対位法的、優雅なアラベスクなど)、18世紀クラヴサン音楽の技法(多彩な装飾音、「バトリ」など)。
ドビュッシー独自の語法としては、ペダルで白鍵と黒鍵の響きを混ぜたり、重音や和音塊を平行移動させたり、いくつもの層を積み重ねて、独特の「音響宇宙」を生み出したこと、ポリリズムやルバートを多用して自在な律動を作り出したことなどがあげられる。
1907年にドビュッシーは、「私はますます音楽というのは色彩と律動づけられた時間でできていると確信するようになった」と書いているが、調性からもリズムからも自由になりながら有機性を失わなかったドビュッシーの在り方を象徴するような言葉である。
『前奏曲集第1巻』が『管弦楽のための映像』の「イベリア」と同時進行していたように、ドビュッシーのピアノ曲はオーケストラ曲やオペラ、声楽曲と密接なかかわりももつものが多い。従って、単にピアノ曲としての解釈にとどまるのではなく、背景となっているテキストや管弦楽の色彩感をとりいれなければ、片手落ちになるだろう。
ドビュッシーの「音響宇宙」にはペダルの使用が不可欠だが、彼の発想はしばしば管弦楽的で、幾重もの音響レベルを明確に弾きわけるタッチとペダリングが求められる。
東洋美術に深い関心をもち、また作品にもとりいれたドビュッシーは、作曲にあたってのモットーを「ものごとの半分まで言って想像力に接ぎ木させる」と表現している。すべてをさらけ出さず、深く静かに潜行させるその姿勢は、東洋人、とりわけ日本人の美意識にもっとも近い作曲家ということができよう。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
フランス近代の印象派を代表する作曲家。長音階・短音階以外の旋法と、機能和声にとらわれない自由な和声法などとを用いて独自の作曲を実行した。ドビュッシーの音楽は、その特徴的な和音構成などで、音の印象を表現するという独特の表現スタイルを確立し、「印象主義音楽(印象派)」と称されている。
演奏家解説 - チッコリーニ,アルド
フランス在住のイタリア人ピアニスト。ナポリ出身。1949年にパリのロン・ティボー国際コンクールに優勝する。1969年にフランスに帰化し、1970年から1983年までパリ音楽院で教鞭を執った。フランス近代音楽の解釈者ならびに擁護者として国際的に著名であり、数多くの曲を録音している。
7. 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲 / ドビュッシー,クロード / 内田 光子
内田」光子さんの演奏は名演とされています。キレの良い演奏ですね。楽譜と共に。
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 練習曲集 第11曲 組み合わされたアルペッジョのための練習曲
1915年、これまで健康の不調と第一次大戦への苦悩などからしばらく作曲ができていなかったドビュッシーだが、ショパンの楽譜を校訂する仕事をきっかけに、創作力をとりもどした。ここで作曲されたのが《12の練習曲》であり、これはショパンに献呈されている。この練習曲では、ただ技巧を追求するための作品として作曲されているわけではない。彼はこの作品を通じて、彼自身の音楽性のあり方を再検討したのであろう。練習曲でありながら、運指法が指示されていないことも特徴の一つであるが、ドビュッシーはこれを意図的におこなっている。つまり、演奏者の腕や手の構造には違いがあるため、各人に合った運指法を各自で追求していくこともまた、課題の一つになっているのである。
6曲ずつの2巻に分けられている。
11.組み合わされたアルペッジョのための / "Pour les arpeges composes"。この作品には曲想表示がない。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
ドビュッシーの旋律や和声に関する才能をよく示している。主要なテーマは、彩られて輝く一連の音符によって曲全体を通じて巧みに移動する。ドビュッシーはいつも安易な旋律を避け、聞き手を思いがけない音の世界へ誘うことを望んだ。
作曲家解説 - ドビュッシー,クロード
フランスの作曲家。
クロード・アシル・ドビュッシーは1862年8月22日、父マニュエルと母ヴィクトリーヌの長男として、パリ西郊約20キロの町サン=ジェルマン=アン=レに生まれた。
ドビュッシーは、ワーグナーを乗り越えるためにフランス固有の美を武器とし、大胆な語法によって20世紀音楽への扉をあけた作曲家である。長調・短調の明確な対比を嫌った彼は、教会旋法、東洋風の5音音階、全音音階などを駆使し、印象派の画家たちが遠近法を回避するために画面を分割したように、平面的、スタティックな美を生み出した。
ドビュッシーのピアニズムには、大きくわけて次の3つの源流がある。モーテ夫人を通じて伝えられたショパンの技法(ビロードのようなタッチと美しい響き、軽やかなリズムなど)、やはりモーテ夫人に目を開かれたバッハの書法(対位法的、優雅なアラベスクなど)、18世紀クラヴサン音楽の技法(多彩な装飾音、「バトリ」など)。
ドビュッシー独自の語法としては、ペダルで白鍵と黒鍵の響きを混ぜたり、重音や和音塊を平行移動させたり、いくつもの層を積み重ねて、独特の「音響宇宙」を生み出したこと、ポリリズムやルバートを多用して自在な律動を作り出したことなどがあげられる。
1907年にドビュッシーは、「私はますます音楽というのは色彩と律動づけられた時間でできていると確信するようになった」と書いているが、調性からもリズムからも自由になりながら有機性を失わなかったドビュッシーの在り方を象徴するような言葉である。
『前奏曲集第1巻』が『管弦楽のための映像』の「イベリア」と同時進行していたように、ドビュッシーのピアノ曲はオーケストラ曲やオペラ、声楽曲と密接なかかわりももつものが多い。従って、単にピアノ曲としての解釈にとどまるのではなく、背景となっているテキストや管弦楽の色彩感をとりいれなければ、片手落ちになるだろう。
ドビュッシーの「音響宇宙」にはペダルの使用が不可欠だが、彼の発想はしばしば管弦楽的で、幾重もの音響レベルを明確に弾きわけるタッチとペダリングが求められる。
東洋美術に深い関心をもち、また作品にもとりいれたドビュッシーは、作曲にあたってのモットーを「ものごとの半分まで言って想像力に接ぎ木させる」と表現している。すべてをさらけ出さず、深く静かに潜行させるその姿勢は、東洋人、とりわけ日本人の美意識にもっとも近い作曲家ということができよう。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
フランス近代の印象派を代表する作曲家。長音階・短音階以外の旋法と、機能和声にとらわれない自由な和声法などとを用いて独自の作曲を実行した。ドビュッシーの音楽は、その特徴的な和音構成などで、音の印象を表現するという独特の表現スタイルを確立し、「印象主義音楽(印象派)」と称されている。
演奏家解説 - 内田 光子
日本出身、英国籍のピアニスト。お茶の水女子大学附属小学校在学中、桐朋学園の「子供のための音楽教室」にて、松岡貞子に学ぶ。父内田藤雄が外交官であったため、12歳で渡欧。1961年からオーストリアのウィーン音楽院(現:ウィーン国立音楽大学)でリヒャルト・ハウザーに師事する。同時期に、留学中の寺田悦子が同音楽院に在籍し、互いに切磋琢磨した。
その後数々のコンクールにも入賞し、ヨーロッパを中心に活躍する日本人ピアニストとして活躍中。