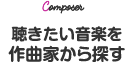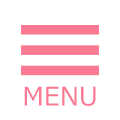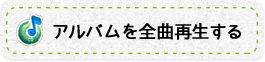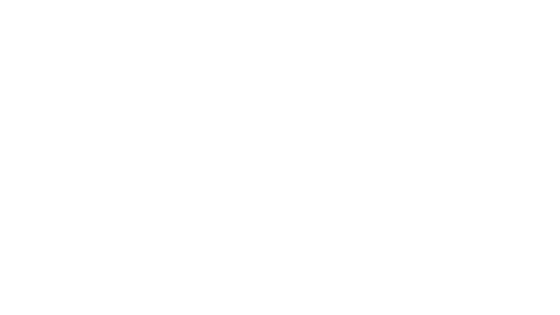![]()
ラフマニノフ ショパンの主題による変奏曲 動画集
ラフマニノフ ショパンの主題による変奏曲の動画集です。

1. ショパンの主題による変奏曲 / ラフマニノフ,セルゲイ / 浦山 瑠衣
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - ショパンの主題による変奏曲
20世紀の初頭、1902年から翌年にかけて作曲された。完成した1903年に出版され、この年の2月にラフマニノフ自身が初演している。
ショパンの《前奏曲集 作品28》の<第20番 ハ短調>を主題としており、そこに22の変奏が続く。尚、初版の楽譜には、第7、10、12変奏を演奏者の任意により省略してよいと書かれている。更に、曲を締めくくる「プレスト」の部分を省略し、その代わりにこの作品の主調であるハ短調の主和音を弾いて曲を終えても良いとされている。この作品には、これらのコメントを反映させた、言わば《ソナタ 第2番》で行われた改訂版は出版されていない。
主題は、ハ短調の4分の4拍子、ラルゴである。この主題は、ショパンの原曲をそのまま用いているわけではなく、長さを短縮してある。
第1変奏は、モデラートとなり、原曲のメロディーが早くも装飾的な音に満ちた1つのラインの中に埋め込まれる。ここで、ラフマニノフは最初の4小節間をこのようなラインのみで構築し、残りの5小節においても、低音域のハ音(主音)を長く響かせることにより、薄いテクスチュアを示している。
第2変奏は、アレグロとなる。第1変奏で右手が弾いたラインが左手へと移る。ここでは、その上に乗って演奏される右手のメロディーの内、各小節の最初の音が演奏されない。そのようにして、主題のフレーズが巧妙に扱われている。
第3変奏では、左右の手がアレグロのまま、2本の糸が織りなすかのような音楽を奏でる。
続く第4変奏で、4分の3拍子となる。また、全24小節と規模がやや大きくなる。主題はffで開始するが、その後、第1変奏から第3変奏までの間、ディナーミクはpやppを中心としていた。一方、この第4変奏では、ディナーミクの頂点が計画的に築かれる。
そして、第5変奏で、4分の4拍子に戻り、メーノ・モッソとなる。
第6変奏は、更にメーノ・モッソとなる。4分の6拍子となるここでは、右手の6連音符と左手の9連音符がポリ・リズムを示す。更に、後半からは、拍頭に分散和音が演奏される。
第7変奏は、前述の通り、省略することができる。ここでアレグロとなり、左右の手が協力し合って付加的な音に満ちた細かい音価のラインを演奏する。
第8変奏には、第7変奏と同じテンポが指示されている。従って、第7変奏を省略した場合には、ここからアレグロとなる。この変奏も、左右の手がポリ・リズムを演奏するが、ここではレッジェーロと指示されている。
第9変奏も引き続き同じテンポが指示されている。ここでは、2つの音域を交互に演奏し、その各々の掛け合いによって音楽が展開されていくラフマニノフに特徴的な手法が見られる。
第10変奏は、前述の通り、省略することができる。ここでピウ・ヴィーヴォとなり、カノンに近い手法で主題が扱われる。最後には、ハ短調の主和音がffで響き、そこにフェルマータが付されている。
続く、第11変奏では、一転して8分の12拍子のレントとなる。従って、第10変奏を省略するか否かにより、この作品の全体の流れが大きく変わってくる。ここでは、非常に半音階的に主題が扱われる。リタルダントとア・テンポによるテンポの変化が目立っている。
モデラートの4分の4拍子で書かれた第12変奏も、省略することができる。この部分の途中には、1小節の4分の2拍子が挿入されている。このようなほんの僅かな範囲の拍子の変化も、ラフマニノフに特徴的な手法の1つである。そして、この変奏の内部において、音楽がドラマティックに展開していくため、第10変奏と同様に、この第12変奏を省略するか否かにより、この作品の全体の流れが大きく変わってくる。
次の第13変奏で、ラルゴの4分の3拍子となる。ここで再び、第9変奏のように、2つの音域を交互に演奏し、その各々の掛け合いによって音楽が展開されていくラフマニノフに特徴的な手法が見られる。
第14変奏は、モデラートの4分の4拍子で書かれている。ここでは、主題がダイナミックな音階として扱われる。メロディーをはっきりと強調する指示が付されている。また、この変奏の最後の1小節は4分の2拍子で書かれており、8分の12拍子となる次の変奏へと続く。
第15変奏では、主調から見た下属調にあたるヘ短調へと転調し、アレグロ・スケルツァンドとなる。この変奏は多声的に書かれている。また、規模が比較的大きく、終結近くでピウ・ヴィーヴォとなる。
続く第16変奏もヘ短調で書かれており、レントとなる。ここでは、メロディーの歌われ方がラフマニノフの手中におさめられ、採譜したルバートのようなリズムで扱われている。
次の第17変奏で変ロ短調となる。つまり、ヘ短調から見た下属調である。また、ここで4分の3拍子のグラーヴェとなる。リズムはほぼ8分音符を主体としており、と中で2小節間挿入される3連音符が効果的である。
第18変奏は、引き続き変ロ短調で書かれている。但し、4分の4拍子のピウ・モッソとなる。ここで再び、ポリ・リズムによる音楽が展開される。
そして、第19変奏で突如、半音低いイ長調に転調する。アレグロ・ヴィヴァーチェの4分の4拍子で書かれたこの部分は、非常に厚い和音のテクスチュアが特徴的である。
更に、第20変奏で、調の変化がドラマティックな音楽の進展に寄与する。プレストで書かれたこの変奏の調号は、♯4つである。概して嬰ハ短調→ホ長調→嬰ハ短調となっており、先立つ第19変奏のイ長調の主和音で開始する。ホ長調の部分では、ラフマニノフの他の作品にも見られるような高音域の細かい音価によるパッセージが特徴的で、ほんの一瞬差し込む光のようである。
続く第21変奏は、異名同音上の同主長調、変ニ長調で開始する。この変奏も、非常にドラマティックに音楽が進展していく。冒頭のアンダンテの部分には、ピウ・ヴィーヴォの部分が続く。この部分には調号がないが、ト音を強調しているため、ハ長調の属音を保続していると考えられる。
そして、この作品全体を締めくくる第22変奏は、ハ長調で書かれている。従って、ここに先立つピウ・ヴィーヴォはやはりハ長調の属音を保続し、この部分への橋渡しをしていたことになる。また、この作品の同主長調へ行き着くまでに、作品の後半で非常にドラマッティックな調を辿ってきたことがわかる。この変奏は、4分の3拍子のマエストーソで書かれており、厚いテクスチュアの和音やポリ・リズム、2つの音域を交互に演奏する掛け合いによる音楽の展開といった、これまで見られた多様な手法で比較的規模が大きく紡ぎ出される。また、前述の通り、メーノ・モッソの後のプレストの部分を省略し、その代わりにこの作品の主調であるハ短調の主和音を弾いて曲を終えても良いとされている。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
作曲家解説 - ラフマニノフ,セルゲイ
ロシアのピアニスト、作曲家、指揮者。苦学してモスクワ音楽院のピアノ科と作曲科を通常より1年早く卒業。特に作曲は大金章という最高成績を受けた。1892年、卒業後すぐに出版した前奏曲嬰ハ短調は、さっそく人気の作品となった。が、交響曲第1番の不評が原因で一時作曲を断念する。1902年、ピアノ協奏曲第2番を自ら初演して表舞台に返り咲き、劇場で指揮者を務めた後、06年にドレスデンに移ってからしばらくは作曲に専念した。09年に渡米、自作を演奏するピアニストとして名声を高めた。ロシア革命の混乱をかわしつつヨーロッパとアメリカで演奏活動を行い、20年代後半はヨーロッパにとどまろうと努力したが、31年にソヴィエト連邦の体制を批判したため、政府はかれの作品の上演を禁止した(これは2年ほどで解除された))。晩年は新たな戦争への危機感からアメリカへ戻った。
ラフマニノフはピアノ演奏、指揮、作曲のいずれにおいても成功を収めたが、すべてに同時に打ち込むことには困難を感じていた。後半生の演奏活動は作曲への集中力を妨げたのか、傑作は初期に多い。
ラフマニノフは、ピアノという楽器の可能性を最大限に引き出すことを追求しつづけた。 驚異的な演奏技術、人並みはずれた大きな手を持っていたと言われるが、自身のピアノ曲では技巧に終始するのではなく、哀愁や情熱を宿した美しい旋律を楽曲へと堅実に組み立てる方法を知っていた。チャイコフスキーを規範とし、あくまで長短調の枠にとどまって後期ロマン派の色彩と叙情性を継承している。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
演奏家解説 - 浦山 瑠衣
日本のピアニスト。京都市立芸術大学音楽学部ピアノ専攻卒業。大学卒業後、渡米。現在、ボストン音楽院修士課程に授業料全額免除の奨学金と、演奏活動のための助成金を学校より授与され留学中。2005年、ピティナ・ピアノコンペティションG級ベスト4賞、2006年同コンペティション特級ファイナリスト。アメリカ国内は元よりイタリア、リトアニア、アルバニア等ヨーロッパ各地でも積極的に演奏活動を行っている。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より