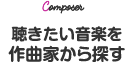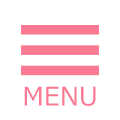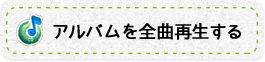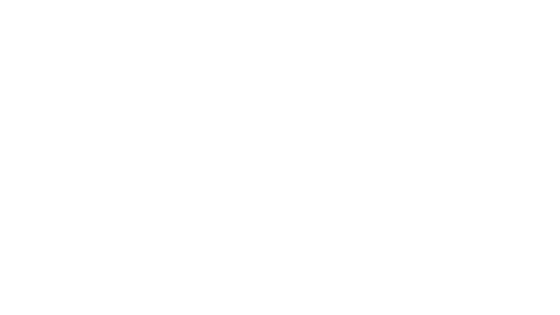![]()
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 動画集
ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲 Op.43 全楽章の動画集です。

1. パガニーニに主題による狂詩曲 / ラフマニノフ,セルゲイ / 市川 雅己
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - パガニーニに主題による狂詩曲
1934年11月7日、ルツェルン湖畔の別荘にて完成されたこの作品にラフマニノフが注いだ時間は、わずか数週間であったという。独奏ピアノとオーケストラという「ピアノ協奏曲」のスタイルで作曲された「狂詩曲」は、パガニーニによる独奏ヴァイオリンのための「24のカプリース(奇想曲)」から第24番の主題をもとに、24の変奏を繰り広げる壮大な「変奏曲」である。
序奏―第1変奏―主題:パガニーニによる主題の断片による8小節間の序奏(4分の2拍子 Allegro vivace イ短調)に続いて、まず第1変奏がおかれ、その後ようやく本来の主題がヴァイオリンのトゥッティであらわれる。
第2-6変奏:独奏ピアノの技巧的なパッセージを中心に音形的な変奏が追及される。
第7変奏:テンポを落とし、主題の8分音符主体の音形的変奏に「ディエス・イレ(怒りの日)」の主題が組み込まれる。
第8-9変奏:第8変奏でテンポをもとに戻し、第7変奏での8分音符主体の音形が引き継がれ、第9変奏では8分3連音符が主体となって、リズム的に切迫してゆく。
第10変奏:4分の4拍子となり、ふたたびディエス・イレの主題がバス声部にあらわれる。
第11変奏:4分3拍子でModeratoにテンポを落とし、弦楽のトレモロと木管楽器による和声と主題の音形を背景に、独奏ピアノによる自由な楽想が展開される。
第12変奏:ここから調性がニ短調となり、「メヌエットのテンポで」という指示のもと、第2ヴァイオリンの性格的な伴奏の上にメヌエットというよりはスケルツォ風のリズミカルなパッセージが展開されるなか、時折主題の断片が顔をのぞかせる。
第13変奏:弦楽器群のトゥッティによる主題の音形変奏に、独奏ピアノによる最強奏の和音が音楽に切迫感を与える。
第14-15変奏:はじめて長調へと転じ(ヘ長調)、主題は8分音符の3連音符に変形されており、この断片が、独奏ピアノによるカデンツァによって開始される第15変奏のなかにあらわれる。
第16-17変奏:4分の2拍子となり、前の変奏におけるヘ長調がドミナントの役割を果たし、ここから変ロ短調へ転じる。主題の原型が断片的にあらわれるも、4分の4拍子となる第17変奏では、独奏ピアノの流動的な音形が主体となって、動機的な要素は一層希薄になる。
第18変奏:4分の3拍子で平行長調である変ニ長調に転じる。テンポをAndanteに落とし、主題動機の反行形がカンタービレ風の旋律へと変容する。この変奏はしばしば独奏曲として抜粋で演奏されることもあるが、調性や動機の変奏方法を前後の関係から徐々に変化させてゆく作曲者の意図を考慮すべきであろう。しかしこのことは、第18変奏がそれほどまでに主題動機を甘美で魅力的な旋律へと変容させていることを逆説的に物語っている。
第19-21変奏:テンポをVivaceに速めて6小節の間奏を挟み、もとの調性であるイ短調を回復し、拍子は4分の4拍子へと変化する。独奏ピアノのアクセントづけされた8分3連音符が変奏の主体となり、続く第20変奏ではテンポをさらに速めて、第7変奏で特徴的だった装飾的なリズムが主体となる。そして第21変奏ではふたたび8分3連音符を主体とし、独奏ピアノによるユニゾンのパッセージを背景に、主題動機が断片的にあらわれる。
第22変奏:16分音符4つという主題動機を構成するリズムが抽出され、これが8分3連音、そして4分3連音へと変容してゆく。主題動機そのものとリズムのみが抽出された動機が対立するなか、後者は変容の過程で淘汰され、独奏ピアノの技巧的なパッセージを背景に主題動機が繰り返しあらわれる。
第23-24変奏:独奏ピアノのカデンツァを挟み、主題が独奏ピアノとオーケストラのトゥッティによるフィナーレへと昇華する。金管楽器群によって高らかに奏されるディエス・イレの主題もくわわり、和音の連打が交差するラフマニノフに典型的な技巧的パッセージとともに頂点を築く。しかし終結直前に弱奏へ転じ、ラフマニノフが華々しく楽曲を結ぶ際に常套的に用いるダクテュルス・リズム(ジャン・ジャジャ・ジャン)を避けるかのように、主題動機の一瞬の回想と弦楽のピッツィカートによって楽曲を閉じる。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
作曲家解説 - ラフマニノフ,セルゲイ
ロシアのピアニスト、作曲家、指揮者。苦学してモスクワ音楽院のピアノ科と作曲科を通常より1年早く卒業。特に作曲は大金章という最高成績を受けた。1892年、卒業後すぐに出版した前奏曲嬰ハ短調は、さっそく人気の作品となった。が、交響曲第1番の不評が原因で一時作曲を断念する。1902年、ピアノ協奏曲第2番を自ら初演して表舞台に返り咲き、劇場で指揮者を務めた後、06年にドレスデンに移ってからしばらくは作曲に専念した。09年に渡米、自作を演奏するピアニストとして名声を高めた。ロシア革命の混乱をかわしつつヨーロッパとアメリカで演奏活動を行い、20年代後半はヨーロッパにとどまろうと努力したが、31年にソヴィエト連邦の体制を批判したため、政府はかれの作品の上演を禁止した(これは2年ほどで解除された))。晩年は新たな戦争への危機感からアメリカへ戻った。
ラフマニノフはピアノ演奏、指揮、作曲のいずれにおいても成功を収めたが、すべてに同時に打ち込むことには困難を感じていた。後半生の演奏活動は作曲への集中力を妨げたのか、傑作は初期に多い。
ラフマニノフは、ピアノという楽器の可能性を最大限に引き出すことを追求しつづけた。 驚異的な演奏技術、人並みはずれた大きな手を持っていたと言われるが、自身のピアノ曲では技巧に終始するのではなく、哀愁や情熱を宿した美しい旋律を楽曲へと堅実に組み立てる方法を知っていた。チャイコフスキーを規範とし、あくまで長短調の枠にとどまって後期ロマン派の色彩と叙情性を継承している。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
演奏家解説 - 市川 雅己
日本のピアニスト。桐朋学園大学、同大学院修士課程を修了。同修論がPTNA研究レポート第一号に初採用後、英国留学、奨学金を得てロンドン大学(RAM)入学、同大学院修了。仏パリ・エコール・ ノルマル音楽院を満点一致の審査員特別賞を得て首席修了。これまで国内外での30余りのコンクール・オーディションで受賞他、リサイタル、交響楽団等の演奏活動を行う。現在、器楽・声楽・室内楽など年20余りの音楽コンクールの審査員、各地の文化事業の役員、実行委員を務める。洗足学園大学講師、全日本ピアノ指導者協会正会員。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
2. パガニーニに主題による狂詩曲 / ラフマニノフ,セルゲイ / コブリン,アレクサンダー
繊細でかつ大胆な演奏です。 「ピティナ・ピアノ曲事典」より
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - パガニーニに主題による狂詩曲
1934年11月7日、ルツェルン湖畔の別荘にて完成されたこの作品にラフマニノフが注いだ時間は、わずか数週間であったという。独奏ピアノとオーケストラという「ピアノ協奏曲」のスタイルで作曲された「狂詩曲」は、パガニーニによる独奏ヴァイオリンのための「24のカプリース(奇想曲)」から第24番の主題をもとに、24の変奏を繰り広げる壮大な「変奏曲」である。
序奏―第1変奏―主題:パガニーニによる主題の断片による8小節間の序奏(4分の2拍子 Allegro vivace イ短調)に続いて、まず第1変奏がおかれ、その後ようやく本来の主題がヴァイオリンのトゥッティであらわれる。
第2-6変奏:独奏ピアノの技巧的なパッセージを中心に音形的な変奏が追及される。
第7変奏:テンポを落とし、主題の8分音符主体の音形的変奏に「ディエス・イレ(怒りの日)」の主題が組み込まれる。
第8-9変奏:第8変奏でテンポをもとに戻し、第7変奏での8分音符主体の音形が引き継がれ、第9変奏では8分3連音符が主体となって、リズム的に切迫してゆく。
第10変奏:4分の4拍子となり、ふたたびディエス・イレの主題がバス声部にあらわれる。
第11変奏:4分3拍子でModeratoにテンポを落とし、弦楽のトレモロと木管楽器による和声と主題の音形を背景に、独奏ピアノによる自由な楽想が展開される。
第12変奏:ここから調性がニ短調となり、「メヌエットのテンポで」という指示のもと、第2ヴァイオリンの性格的な伴奏の上にメヌエットというよりはスケルツォ風のリズミカルなパッセージが展開されるなか、時折主題の断片が顔をのぞかせる。
第13変奏:弦楽器群のトゥッティによる主題の音形変奏に、独奏ピアノによる最強奏の和音が音楽に切迫感を与える。
第14-15変奏:はじめて長調へと転じ(ヘ長調)、主題は8分音符の3連音符に変形されており、この断片が、独奏ピアノによるカデンツァによって開始される第15変奏のなかにあらわれる。
第16-17変奏:4分の2拍子となり、前の変奏におけるヘ長調がドミナントの役割を果たし、ここから変ロ短調へ転じる。主題の原型が断片的にあらわれるも、4分の4拍子となる第17変奏では、独奏ピアノの流動的な音形が主体となって、動機的な要素は一層希薄になる。
第18変奏:4分の3拍子で平行長調である変ニ長調に転じる。テンポをAndanteに落とし、主題動機の反行形がカンタービレ風の旋律へと変容する。この変奏はしばしば独奏曲として抜粋で演奏されることもあるが、調性や動機の変奏方法を前後の関係から徐々に変化させてゆく作曲者の意図を考慮すべきであろう。しかしこのことは、第18変奏がそれほどまでに主題動機を甘美で魅力的な旋律へと変容させていることを逆説的に物語っている。
第19-21変奏:テンポをVivaceに速めて6小節の間奏を挟み、もとの調性であるイ短調を回復し、拍子は4分の4拍子へと変化する。独奏ピアノのアクセントづけされた8分3連音符が変奏の主体となり、続く第20変奏ではテンポをさらに速めて、第7変奏で特徴的だった装飾的なリズムが主体となる。そして第21変奏ではふたたび8分3連音符を主体とし、独奏ピアノによるユニゾンのパッセージを背景に、主題動機が断片的にあらわれる。
第22変奏:16分音符4つという主題動機を構成するリズムが抽出され、これが8分3連音、そして4分3連音へと変容してゆく。主題動機そのものとリズムのみが抽出された動機が対立するなか、後者は変容の過程で淘汰され、独奏ピアノの技巧的なパッセージを背景に主題動機が繰り返しあらわれる。
第23-24変奏:独奏ピアノのカデンツァを挟み、主題が独奏ピアノとオーケストラのトゥッティによるフィナーレへと昇華する。金管楽器群によって高らかに奏されるディエス・イレの主題もくわわり、和音の連打が交差するラフマニノフに典型的な技巧的パッセージとともに頂点を築く。しかし終結直前に弱奏へ転じ、ラフマニノフが華々しく楽曲を結ぶ際に常套的に用いるダクテュルス・リズム(ジャン・ジャジャ・ジャン)を避けるかのように、主題動機の一瞬の回想と弦楽のピッツィカートによって楽曲を閉じる。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
作曲家解説 - ラフマニノフ,セルゲイ
ロシアのピアニスト、作曲家、指揮者。苦学してモスクワ音楽院のピアノ科と作曲科を通常より1年早く卒業。特に作曲は大金章という最高成績を受けた。1892年、卒業後すぐに出版した前奏曲嬰ハ短調は、さっそく人気の作品となった。が、交響曲第1番の不評が原因で一時作曲を断念する。1902年、ピアノ協奏曲第2番を自ら初演して表舞台に返り咲き、劇場で指揮者を務めた後、06年にドレスデンに移ってからしばらくは作曲に専念した。09年に渡米、自作を演奏するピアニストとして名声を高めた。ロシア革命の混乱をかわしつつヨーロッパとアメリカで演奏活動を行い、20年代後半はヨーロッパにとどまろうと努力したが、31年にソヴィエト連邦の体制を批判したため、政府はかれの作品の上演を禁止した(これは2年ほどで解除された))。晩年は新たな戦争への危機感からアメリカへ戻った。
ラフマニノフはピアノ演奏、指揮、作曲のいずれにおいても成功を収めたが、すべてに同時に打ち込むことには困難を感じていた。後半生の演奏活動は作曲への集中力を妨げたのか、傑作は初期に多い。
ラフマニノフは、ピアノという楽器の可能性を最大限に引き出すことを追求しつづけた。 驚異的な演奏技術、人並みはずれた大きな手を持っていたと言われるが、自身のピアノ曲では技巧に終始するのではなく、哀愁や情熱を宿した美しい旋律を楽曲へと堅実に組み立てる方法を知っていた。チャイコフスキーを規範とし、あくまで長短調の枠にとどまって後期ロマン派の色彩と叙情性を継承している。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
演奏家解説 - コブリン,アレクサンダー
ロシアのピアニスト。グラスゴー国際ピアノコンクール優勝(1998年)、ブゾーニ国際コンクール優勝(1999年)、ショパン国際ピアノコンクール第3位(2000年)、第12回ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクール優勝(2005年)、浜松国際ピアノコンクール最高位(2003年11月)入賞し、ヨーロッパやアジア、南米で精力的に演奏活動を展開。 演奏活動の傍ら、モスクワ国立グネーシン音楽院で後進の指導にあたっている。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
3. パガニーニに主題による狂詩曲 / ラフマニノフ,セルゲイ / ラフマニノフ,セルゲイ
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - パガニーニに主題による狂詩曲
1934年11月7日、ルツェルン湖畔の別荘にて完成されたこの作品にラフマニノフが注いだ時間は、わずか数週間であったという。独奏ピアノとオーケストラという「ピアノ協奏曲」のスタイルで作曲された「狂詩曲」は、パガニーニによる独奏ヴァイオリンのための「24のカプリース(奇想曲)」から第24番の主題をもとに、24の変奏を繰り広げる壮大な「変奏曲」である。
序奏―第1変奏―主題:パガニーニによる主題の断片による8小節間の序奏(4分の2拍子 Allegro vivace イ短調)に続いて、まず第1変奏がおかれ、その後ようやく本来の主題がヴァイオリンのトゥッティであらわれる。
第2-6変奏:独奏ピアノの技巧的なパッセージを中心に音形的な変奏が追及される。
第7変奏:テンポを落とし、主題の8分音符主体の音形的変奏に「ディエス・イレ(怒りの日)」の主題が組み込まれる。
第8-9変奏:第8変奏でテンポをもとに戻し、第7変奏での8分音符主体の音形が引き継がれ、第9変奏では8分3連音符が主体となって、リズム的に切迫してゆく。
第10変奏:4分の4拍子となり、ふたたびディエス・イレの主題がバス声部にあらわれる。
第11変奏:4分3拍子でModeratoにテンポを落とし、弦楽のトレモロと木管楽器による和声と主題の音形を背景に、独奏ピアノによる自由な楽想が展開される。
第12変奏:ここから調性がニ短調となり、「メヌエットのテンポで」という指示のもと、第2ヴァイオリンの性格的な伴奏の上にメヌエットというよりはスケルツォ風のリズミカルなパッセージが展開されるなか、時折主題の断片が顔をのぞかせる。
第13変奏:弦楽器群のトゥッティによる主題の音形変奏に、独奏ピアノによる最強奏の和音が音楽に切迫感を与える。
第14-15変奏:はじめて長調へと転じ(ヘ長調)、主題は8分音符の3連音符に変形されており、この断片が、独奏ピアノによるカデンツァによって開始される第15変奏のなかにあらわれる。
第16-17変奏:4分の2拍子となり、前の変奏におけるヘ長調がドミナントの役割を果たし、ここから変ロ短調へ転じる。主題の原型が断片的にあらわれるも、4分の4拍子となる第17変奏では、独奏ピアノの流動的な音形が主体となって、動機的な要素は一層希薄になる。
第18変奏:4分の3拍子で平行長調である変ニ長調に転じる。テンポをAndanteに落とし、主題動機の反行形がカンタービレ風の旋律へと変容する。この変奏はしばしば独奏曲として抜粋で演奏されることもあるが、調性や動機の変奏方法を前後の関係から徐々に変化させてゆく作曲者の意図を考慮すべきであろう。しかしこのことは、第18変奏がそれほどまでに主題動機を甘美で魅力的な旋律へと変容させていることを逆説的に物語っている。
第19-21変奏:テンポをVivaceに速めて6小節の間奏を挟み、もとの調性であるイ短調を回復し、拍子は4分の4拍子へと変化する。独奏ピアノのアクセントづけされた8分3連音符が変奏の主体となり、続く第20変奏ではテンポをさらに速めて、第7変奏で特徴的だった装飾的なリズムが主体となる。そして第21変奏ではふたたび8分3連音符を主体とし、独奏ピアノによるユニゾンのパッセージを背景に、主題動機が断片的にあらわれる。
第22変奏:16分音符4つという主題動機を構成するリズムが抽出され、これが8分3連音、そして4分3連音へと変容してゆく。主題動機そのものとリズムのみが抽出された動機が対立するなか、後者は変容の過程で淘汰され、独奏ピアノの技巧的なパッセージを背景に主題動機が繰り返しあらわれる。
第23-24変奏:独奏ピアノのカデンツァを挟み、主題が独奏ピアノとオーケストラのトゥッティによるフィナーレへと昇華する。金管楽器群によって高らかに奏されるディエス・イレの主題もくわわり、和音の連打が交差するラフマニノフに典型的な技巧的パッセージとともに頂点を築く。しかし終結直前に弱奏へ転じ、ラフマニノフが華々しく楽曲を結ぶ際に常套的に用いるダクテュルス・リズム(ジャン・ジャジャ・ジャン)を避けるかのように、主題動機の一瞬の回想と弦楽のピッツィカートによって楽曲を閉じる。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
作曲家解説 - ラフマニノフ,セルゲイ
ロシアのピアニスト、作曲家、指揮者。苦学してモスクワ音楽院のピアノ科と作曲科を通常より1年早く卒業。特に作曲は大金章という最高成績を受けた。1892年、卒業後すぐに出版した前奏曲嬰ハ短調は、さっそく人気の作品となった。が、交響曲第1番の不評が原因で一時作曲を断念する。1902年、ピアノ協奏曲第2番を自ら初演して表舞台に返り咲き、劇場で指揮者を務めた後、06年にドレスデンに移ってからしばらくは作曲に専念した。09年に渡米、自作を演奏するピアニストとして名声を高めた。ロシア革命の混乱をかわしつつヨーロッパとアメリカで演奏活動を行い、20年代後半はヨーロッパにとどまろうと努力したが、31年にソヴィエト連邦の体制を批判したため、政府はかれの作品の上演を禁止した(これは2年ほどで解除された))。晩年は新たな戦争への危機感からアメリカへ戻った。
ラフマニノフはピアノ演奏、指揮、作曲のいずれにおいても成功を収めたが、すべてに同時に打ち込むことには困難を感じていた。後半生の演奏活動は作曲への集中力を妨げたのか、傑作は初期に多い。
ラフマニノフは、ピアノという楽器の可能性を最大限に引き出すことを追求しつづけた。 驚異的な演奏技術、人並みはずれた大きな手を持っていたと言われるが、自身のピアノ曲では技巧に終始するのではなく、哀愁や情熱を宿した美しい旋律を楽曲へと堅実に組み立てる方法を知っていた。チャイコフスキーを規範とし、あくまで長短調の枠にとどまって後期ロマン派の色彩と叙情性を継承している。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
演奏家解説 - ラフマニノフ,セルゲイ
ロシアの作曲家。ピアニストとしても歴史的な名演を残している。
2Mに近い体躯を持つ。マルファン症候群(=遺伝病。一般に身長は高く、指が長く、しばしば強度の憂鬱症を伴う)だったのではないかともいわれている。確かに彼は憂鬱な一生を過ごしていたようである。
ロシア革命を避けてアメリカに亡命した後半生は当時最高のピアニストとして大活躍をしてたのにもかかわらず、いつも何かに悩んでいたようである。しかし、その悩みが彼独自のメランコリックでロマンティックな作風につながったともいえそうである。
4. パガニーニに主題による狂詩曲 / ラフマニノフ,セルゲイ / ルービンシュタイン,アルトゥール
Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner, conductor Recorded: January 16, 1956
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - パガニーニに主題による狂詩曲
1934年11月7日、ルツェルン湖畔の別荘にて完成されたこの作品にラフマニノフが注いだ時間は、わずか数週間であったという。独奏ピアノとオーケストラという「ピアノ協奏曲」のスタイルで作曲された「狂詩曲」は、パガニーニによる独奏ヴァイオリンのための「24のカプリース(奇想曲)」から第24番の主題をもとに、24の変奏を繰り広げる壮大な「変奏曲」である。
序奏―第1変奏―主題:パガニーニによる主題の断片による8小節間の序奏(4分の2拍子 Allegro vivace イ短調)に続いて、まず第1変奏がおかれ、その後ようやく本来の主題がヴァイオリンのトゥッティであらわれる。
第2-6変奏:独奏ピアノの技巧的なパッセージを中心に音形的な変奏が追及される。
第7変奏:テンポを落とし、主題の8分音符主体の音形的変奏に「ディエス・イレ(怒りの日)」の主題が組み込まれる。
第8-9変奏:第8変奏でテンポをもとに戻し、第7変奏での8分音符主体の音形が引き継がれ、第9変奏では8分3連音符が主体となって、リズム的に切迫してゆく。
第10変奏:4分の4拍子となり、ふたたびディエス・イレの主題がバス声部にあらわれる。
第11変奏:4分3拍子でModeratoにテンポを落とし、弦楽のトレモロと木管楽器による和声と主題の音形を背景に、独奏ピアノによる自由な楽想が展開される。
第12変奏:ここから調性がニ短調となり、「メヌエットのテンポで」という指示のもと、第2ヴァイオリンの性格的な伴奏の上にメヌエットというよりはスケルツォ風のリズミカルなパッセージが展開されるなか、時折主題の断片が顔をのぞかせる。
第13変奏:弦楽器群のトゥッティによる主題の音形変奏に、独奏ピアノによる最強奏の和音が音楽に切迫感を与える。
第14-15変奏:はじめて長調へと転じ(ヘ長調)、主題は8分音符の3連音符に変形されており、この断片が、独奏ピアノによるカデンツァによって開始される第15変奏のなかにあらわれる。
第16-17変奏:4分の2拍子となり、前の変奏におけるヘ長調がドミナントの役割を果たし、ここから変ロ短調へ転じる。主題の原型が断片的にあらわれるも、4分の4拍子となる第17変奏では、独奏ピアノの流動的な音形が主体となって、動機的な要素は一層希薄になる。
第18変奏:4分の3拍子で平行長調である変ニ長調に転じる。テンポをAndanteに落とし、主題動機の反行形がカンタービレ風の旋律へと変容する。この変奏はしばしば独奏曲として抜粋で演奏されることもあるが、調性や動機の変奏方法を前後の関係から徐々に変化させてゆく作曲者の意図を考慮すべきであろう。しかしこのことは、第18変奏がそれほどまでに主題動機を甘美で魅力的な旋律へと変容させていることを逆説的に物語っている。
第19-21変奏:テンポをVivaceに速めて6小節の間奏を挟み、もとの調性であるイ短調を回復し、拍子は4分の4拍子へと変化する。独奏ピアノのアクセントづけされた8分3連音符が変奏の主体となり、続く第20変奏ではテンポをさらに速めて、第7変奏で特徴的だった装飾的なリズムが主体となる。そして第21変奏ではふたたび8分3連音符を主体とし、独奏ピアノによるユニゾンのパッセージを背景に、主題動機が断片的にあらわれる。
第22変奏:16分音符4つという主題動機を構成するリズムが抽出され、これが8分3連音、そして4分3連音へと変容してゆく。主題動機そのものとリズムのみが抽出された動機が対立するなか、後者は変容の過程で淘汰され、独奏ピアノの技巧的なパッセージを背景に主題動機が繰り返しあらわれる。
第23-24変奏:独奏ピアノのカデンツァを挟み、主題が独奏ピアノとオーケストラのトゥッティによるフィナーレへと昇華する。金管楽器群によって高らかに奏されるディエス・イレの主題もくわわり、和音の連打が交差するラフマニノフに典型的な技巧的パッセージとともに頂点を築く。しかし終結直前に弱奏へ転じ、ラフマニノフが華々しく楽曲を結ぶ際に常套的に用いるダクテュルス・リズム(ジャン・ジャジャ・ジャン)を避けるかのように、主題動機の一瞬の回想と弦楽のピッツィカートによって楽曲を閉じる。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
作曲家解説 - ラフマニノフ,セルゲイ
ロシアのピアニスト、作曲家、指揮者。苦学してモスクワ音楽院のピアノ科と作曲科を通常より1年早く卒業。特に作曲は大金章という最高成績を受けた。1892年、卒業後すぐに出版した前奏曲嬰ハ短調は、さっそく人気の作品となった。が、交響曲第1番の不評が原因で一時作曲を断念する。1902年、ピアノ協奏曲第2番を自ら初演して表舞台に返り咲き、劇場で指揮者を務めた後、06年にドレスデンに移ってからしばらくは作曲に専念した。09年に渡米、自作を演奏するピアニストとして名声を高めた。ロシア革命の混乱をかわしつつヨーロッパとアメリカで演奏活動を行い、20年代後半はヨーロッパにとどまろうと努力したが、31年にソヴィエト連邦の体制を批判したため、政府はかれの作品の上演を禁止した(これは2年ほどで解除された))。晩年は新たな戦争への危機感からアメリカへ戻った。
ラフマニノフはピアノ演奏、指揮、作曲のいずれにおいても成功を収めたが、すべてに同時に打ち込むことには困難を感じていた。後半生の演奏活動は作曲への集中力を妨げたのか、傑作は初期に多い。
ラフマニノフは、ピアノという楽器の可能性を最大限に引き出すことを追求しつづけた。 驚異的な演奏技術、人並みはずれた大きな手を持っていたと言われるが、自身のピアノ曲では技巧に終始するのではなく、哀愁や情熱を宿した美しい旋律を楽曲へと堅実に組み立てる方法を知っていた。チャイコフスキーを規範とし、あくまで長短調の枠にとどまって後期ロマン派の色彩と叙情性を継承している。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
演奏家解説 - ルービンシュタイン,アルトゥール
ポーランド出身のピアニスト。「ショパン弾き」と言われるほどショパンの演奏は自然で気品に満ちている。90歳近くまで現役として演奏を続けていたため、録音が残されている。ショパンのイメージが強いが実は他の作曲家、室内楽での演奏(録音)にも名演が数多く存在する。