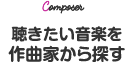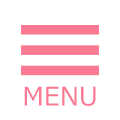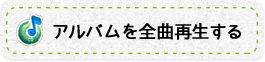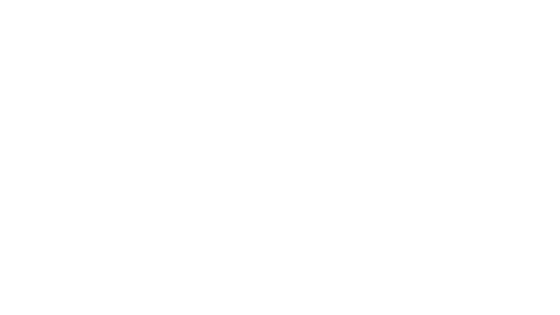![]()
スクリャービン 練習曲Op.8 全曲 動画集
スクリャービン 練習曲 Op.8 全12曲の動画集です。

1. 12の練習曲 作品8 全曲 / スクリャービン,アレクサンドル / ソフロニツキー,ヴラディーミル
この曲の詳細を見る ▼
楽曲解説 - 12の練習曲 作品8 全曲
スクリャービンが22歳の時に書き始められ、翌年に完成した。この練習曲集は、ペテルブルグ音楽院の後援者であり音楽出版業者でもあるべリャーエフが出版をすすめた。この練習曲集の作曲にあたり、スクリャービンがショパンの練習曲集を意識して12曲で1つのまとまりをなすように構成したことが、べリャーエフにあてた手紙からわかっている。なお、ベリャーエフは、この作品を出版した後のスクリャービンの演奏旅行も企画している。実際にスクリャービンは、1895年にはドイツ、スイス、イタリア、ベルギーへ、1896年にはパリ、ブリュッセル、ベルリン、アムステルダム、ハーグ、ローマへ旅している。
第1曲目は、3連符を多用する練習曲。3連符は重音の連打と単音の組み合わせからできている。主として、右手の3連符の3つ目の音がメロディーを構成する。
第2曲目は、スクリャービンに特有のポリ・リズムの練習曲。5連符を基調としている。スクリャービンは、この曲のような3対5の数比を特に好んで用いた。テヌートやスタッカート、スラーなど、多様なタッチが求められる。30小節足らずで、演奏時間も約1分と短い曲ではあるが、曲が進むにつれ左手の音域が広がっていくなど、推進力の変化がみられる。なお、幅広い音域を扱う左手の分散和音は、右手を痛めたピアニストというスクリャービンならではの音形と見ることもできる。
第3曲目は、オクターヴと単音を交互に弾くトレモロのような練習曲。両手でこの形を弾く部分では、オクターヴと単音の位置がずれている。また、いずれかの手のみがこの形を弾く部分では、ポリ・リズムを構成する。8分の6拍子のこの曲では、4分の3拍子としてのリズムやアーティキュレーションももち合わせ、複雑な構成を見せている。なお、スクリャービンはこの曲の冒頭に「テンペストーゾ」という指示を書いたものの、実際にはこの語が充分に曲の性格を示していないと感じ、気に入らなかったという。
第4曲目は、スクリャービンに特有のポリ・リズムの練習曲。5連符を基調としている。第2曲目と同様に、3対5の数比がみられる。しかし、その曲想は第2番とは異なり、こちらはアラベスクのような趣を持つ。
第5曲目は、オクターヴ、2音間のスラー、跳躍がキーワードとなる練習曲。後半からは、基本音価が8分音符の3連符となる。スクリャービンは当初、この曲のテンポをアレグロとしていたが、気に入らず、「ブリオーゾ」と改めた。しかし、それでもこの曲の性格を充分に示していないとして、満足することはなかったという。
第6曲目は、6度の重音の練習曲。冒頭でコン・グラツィアと指示されているように、スクリャービンの練習曲の中では穏やかな性格の曲となっている。
第7曲目は、拍の区切りとずらして3連音符を弾くクロス・フレーズの練習曲。終始一貫して「pp-p」のディナーミクの中で急速に弾くことが求められる。なお、生涯、好んで用い続けたポリ・リズムとは異なり、このクロス・フレーズは晩年の作品になるにつれ、影をひそめていく。
第8曲目は、メロディーに内声としての和音がつけられた練習曲。再現部では、ポリ・リズムとなる。左手の弾くバス・ラインは、対旋律の役割も担う。そして、ポコ・ピウ・ヴィーヴォとなる中間部で、右手が8分音符と3連符の組み合わせが印象的なメロディーを奏でる。そこには、和音を主体とした左手が添えられる。この曲は、初恋の人と言われるナターリア・セケリーナに寄せられていることから、「ナターリアのレント」と呼ばれており、叙情的な美しさが大変好まれている。
第9曲目は、16分音符、8分音符、3連音符など、多様な音価によって、両手のオクターヴにポリ・リズムをもたらす。ディナーミクの頂点は「ff 」で、「pppp 」で曲を閉じるため、非常に幅広いディナーミクを表現することになる。中間部は、コラール風となっており、左右の拍のずれがある種の浮遊感を生み出している。作品8の中では最も規模の大きな練習曲となっている。
第10曲目は、右手は重音を、左手は跳躍音程を弾く練習曲。右手の重音は長3度の響きをもち、4度音程で記譜されているところでも、響きは長3度となっている。また、3部形式で書かれた他の練習曲とは異なり、2部形式で書かれている。
第11曲目は、メロディーと内声、バスの3層のテクスチュアで構成されている。内声の和音は両手を交差させて弾く。
第12曲目は、オクターヴと跳躍音程の織り交ぜ、和音の連打等、複雑な見かけをしている練習曲。再現部では、オクターヴのメロディーに両手の和音の連打が伴われる。なお、この曲は、スクリャービン自身が大変好んで演奏したと言われている。
「ピティナ・ピアノ曲事典」より
作曲家解説 - スクリャービン,アレクサンドル
ロシアの作曲家、ピアニスト。10度音程が掴めない程度の手の持ち主だったにもかかわらず、学生時代の同級生ヨゼフ・レヴィーンらと、超絶技巧の難曲の制覇数をめぐって熾烈な競争を無理に続け、ついに右手首を故障するに至った。回復するまでの間に、左手を特訓するとともに、ピアニストとしての挫折感から作曲にも力を注ぐようになる。右手以上の運動量を要求され、広い音域を駆け巡ることから「左手のコサック」と呼ばれる独自のピアノ書法を編み出した。1900年ごろから神智学に傾倒し「神秘和音」という独自の響きを用いた楽曲を作曲した。
音を聴くと色が見える「色聴感覚」保持者としても有名。
演奏家解説 - ソフロニツキー,ヴラディーミル
アレクサンドル・スクリャービンの信奉者にしてその演奏様式の継承者であり、その遺児エレーナと結婚した。妻エレナと初めて出逢った時にはスクリャービンは鬼籍に入っていたため、ソフロニツキーは公的にも私的にも、生前に岳父と知り合うことはなかった。しかしながらスクリャービン未亡人ヴェーラによって、スクリャービンの後期作品の最も正統的な演奏家として認められた。ソフロニツキーの演奏は、即興的でニュアンスに富んだ雰囲気と、軽く柔らかいタッチにおいてスクリャービン本人の演奏の特色を受け継いでおり、実際にソフロニツキーによるスクリャービン作品の録音は、比類ない演奏として多くから認められている。他にはショパンにも近親感を感じていたらしい。